こちらの記事も読まれています

学区外の小学校に通う方法はある?学区変更ができるケースや必要書類
そもそも学区とは
公立の小学校であれば、学区内の学校に通うのが当たり前と思っている人は多いのではないでしょうか?実は、学区外の小学校に通う方法はいくつかあります。今回の記事では、そもそも学区はどのように決められているのか、また学区外の小学校に通う方法や必要書類などについて詳しく解説します。
※この記事の内容は、2025年9月16日に更新されたものです。
学区とは
公立の小学校の多くは市区町村立となっており、その市区町村ごとに通学できる範囲を分けた区域のことを「学区」と呼びます。「通学区域」や「校区」と呼ぶ場合もあるようです。
文部科学省では、「通学区域」としてこのように説明されています。
“
就学校の指定をする際の判断基準として、市町村教育委員会があらかじめ設定した区域をいう。 この「通学区域」については、法令上の定めはなく、就学校の指定が恣意的に行われたり、保護者にいたずらに不公平感を与えたりすることのないようにすることなどを目的として、道路や河川等の地理的状況、地域社会がつくられてきた長い歴史的経緯や住民感情等それぞれの地域の実態を踏まえ、各市町村教育委員会の判断に基づいて設定されている。
出典: 「よくわかる用語解説」/文部科学省
「地理的状況」「地域の実態」などというとわかりづらいですが、実際には以下のようなことを踏まえて、通う学区・学校が決められています。
- 基本的には徒歩圏内
- 交通量の多い道はなるべく横断させない
- 危険な道は通らない
- 人口ができるだけ偏らない など
もし通学区域内の人口増加により人口が偏る場合には、学校を増改築したり、多目的教室を教室として使用したりと、基本的には通学区域そのものが変更されることは少ないようです。
また、自治体によっては、公立であっても学区を跨いで学校を選択できる場合もあります。この制度のことを「学校選択制」と呼びます。
学校選択制度の種類
学校選択制を実施している自治体は、2012年時点で246ありました。文部科学省の資料によると、学校選択制を実施している自治体は年々増加しているようです。なお、学校選択制を取り入れている場合は、人気のある学校は一部抽選になることもあるようです。
学校選択制度にはいくつか種類がありますので、それぞれ詳しく見てみましょう。
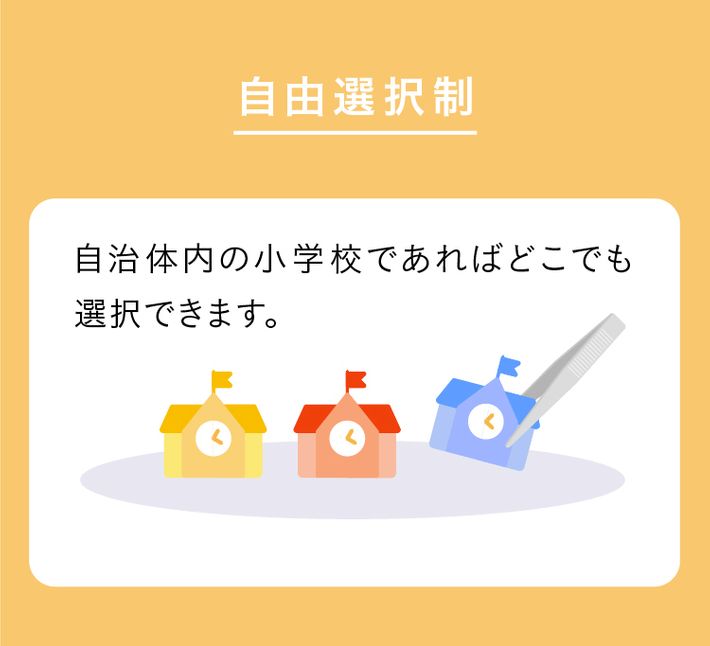
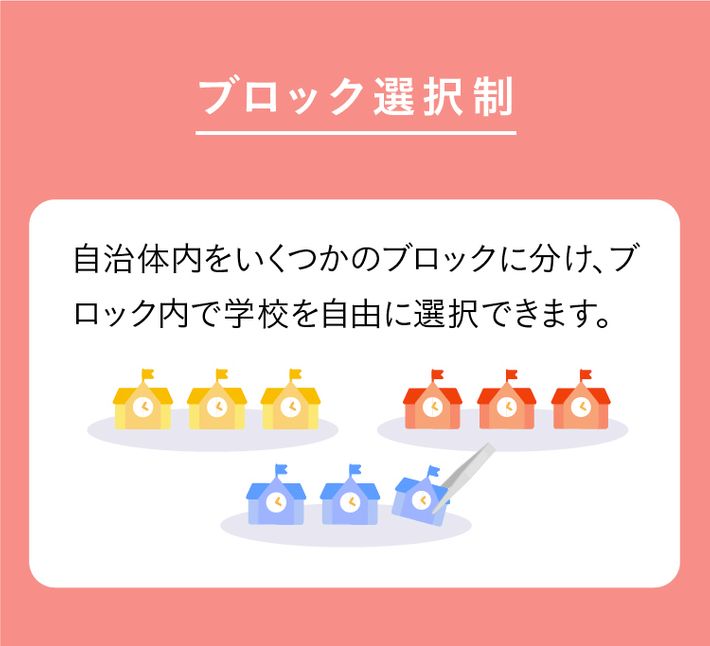
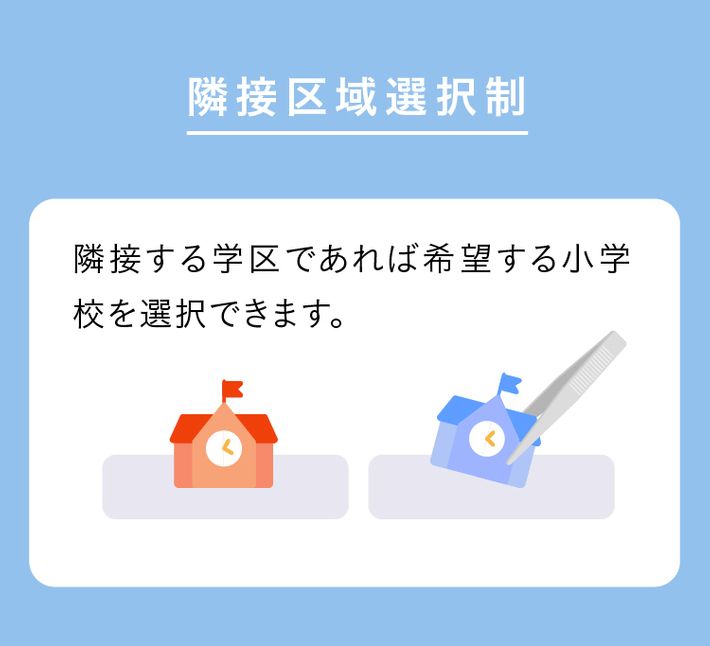
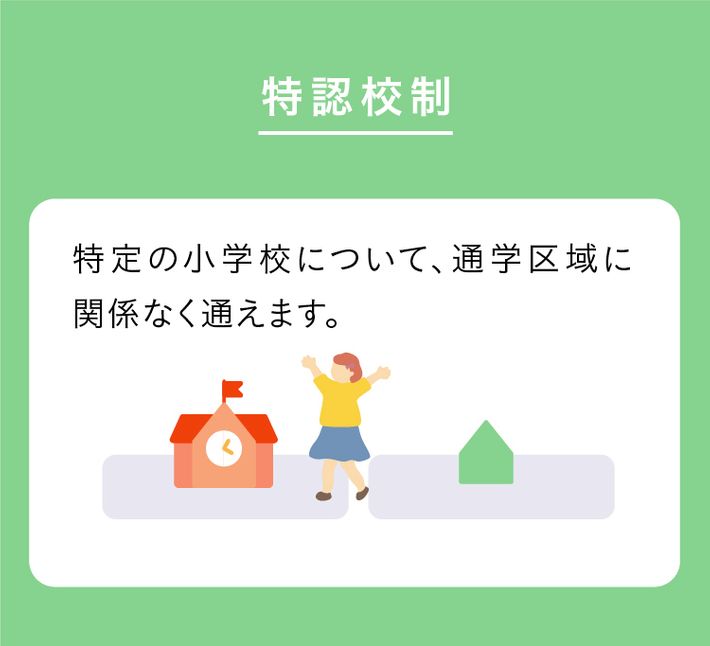
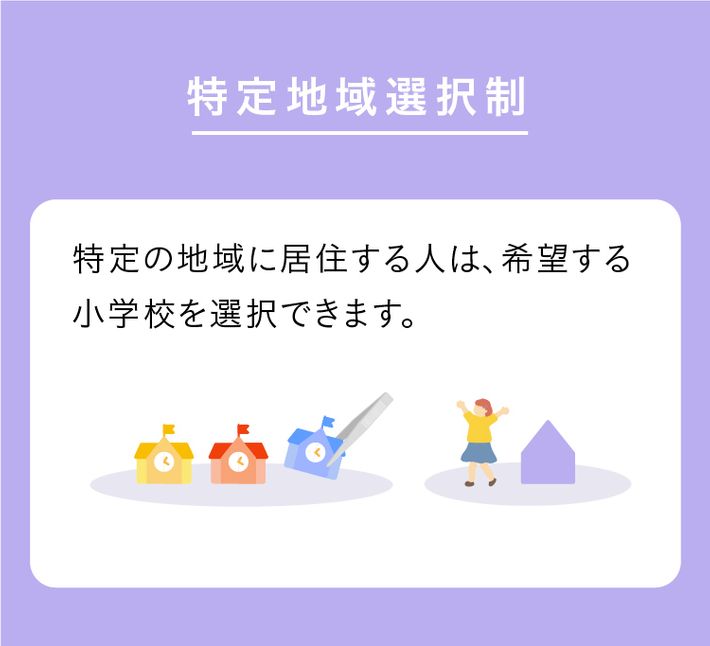
小学校を学区外に変更する方法と変更理由
通学区域を変更して、学区外の小学校に通いたい場合は、どうすればいいのでしょうか?
法律では以下のように定められています。
“
学校教育法施行令 第九条 児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小学校、中学校(併設型中学校を除く。)又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
出典: 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)/e-Gov法令検索
つまり、特別な事情により学区以外の学校への通学を希望する場合には、学区外通学許可の変更申請書や証明書などを提出して、承諾を得る必要があるといえそうです。(申請書は各自治体でもらうことができます。)
「特別な事情」とは、たとえば以下のようなケースです。
引っ越し

iStock.com/Morsa Images

30代ママ
引っ越しに伴う学区外への通学の変更申請をして、学区外の小学校への通学が認められたというママの声がありました。引っ越しに伴う学区外への通学は、以下の理由であれば認められる場合もあるとのことです。
- 小学校の学年途中に転居等した際に、現在の学校に引き続き通学する。
- 小学校の隣接する学区へ転居等した際に、現在の学校に引き続き通学する。
- 中学校在籍途中に転居等した際に、現在の学校に引き続き通学する。
- 公共事業による代替地に転居した際に、現在の学校に引き続き通学する。
- 転居予定先の学区の学校へ、転居する前から通学する。
- 住居の改築などで、一時的に学区外に転居するが、現在の学校に引き続き通学する。
通学距離
40代ママ
指定されている学区よりも、隣の学区にある小学校の方が家からの距離が近いため、学区変更を希望しています。
30代ママ
通学区域の小学校よりも距離が近い小学校があったため、事前に役所に電話をして通学区域変更が可能なのか、必要書類はどんなものかなどを問い合わせました。
指定された学校までの通学距離を理由に、学区の変更を検討するママもいるようです。
- 地理的条件により、指定された学校に通学するのが困難な場合に、平易に通学できる学校に通学する。(距離だけを理由にした申請には応じられない場合があります)
ただ、地理的な条件のみでの学区の変更は受理されない場合もあるそうです。通学距離による学校変更を検討する場合は、自治体に確認してみましょう。
学童保育
30代ママ
共働きなのですが、入学予定の小学校には学童がありませんでした。そのため、学童保育をしている小学校はどこか、手続き方法などを調べたりしました。
- 共働き等しているため、学区外の学童保育を実施している学校に通学する。
指定されている学区には学童保育がない場合や、学童保育が定員の場合などは、状況に応じて通う小学校の変更が認められることもあるとのことです。
家庭の事情

iStock.com/alvarez
40代ママ
上の子の中学校の近くにある小学校の方が通いやすいため、学区変更を検討しました。役所に電話して、手続き方法や必要書類を教えてもらいました。
- 共働き等しているため、学区外の預託する親戚等または勤務先のある学区の学校に通学する。
- 該当するいずれかの理由により兄弟姉妹が学区外の学校に通学している場合に、その兄弟姉妹と同じ学校に通学する。
すでに兄妹が学区外の学校へ通学している場合や、学区外の親戚に預ける場合など、事情に応じて学区の変更が受理されることもあるそうです。
その他の理由
- 許可学区に指定された地区に居住している場合に、許可された学校に通学する。
- 事情により、現在の居住地に住民登録ができない場合に、実際に居住している学区の学校に通学する。
- 特殊学級のある学校へ通学する。
- 心身に著しい疾患があり、転居等による転校に支障がある場合に現在の学校に引き続き通学する。
- 転居等により学区が変わったが、過去に長期欠席があるなど、性格・精神の状態から転校に支障があると認められる場合に、現在の学校に引き続き通学する。
その他、上記の理由によって学区外の学校への通学が認められることもあるとのことです。通学区域の変更を検討している場合は、あらかじめお住まいの自治体に確認してみましょう。
学区外の小学校に通いたい場合の手続きと必要書類
では、学区外の小学校に通いたい場合、具体的にはどんな手続きをすればいいのでしょうか?自治体によりますが、前年度の秋ごろに学校を変更したい旨を申請手続きをして、翌2月ごろに学区外就学の可否通知が届くところが多いようです。必要書類についても自治体によりますが、申請書のほか、学区外就学変更を希望する理由を示した証明書などが必要になります。
【学区外就学手続きの必要書類の例】
- 心身の故障等、身体的な理由の場合・・・医師の診断書
- 住所変更が確定していて、変更予定地の学校への通学を希望する場合・・・転居先の住所及び転居予定日を確認できる書類(契約書等)
- 住宅の建て替え等により、一時校区外へ転出するが、現住所または現在の校区内に戻ってくることが確定していて、今までの学校への通学を希望する場合・・・戻ってくることが明らかであると確認できる書類(契約書等)
- 共働き家庭またはひとり親家庭で、就学を希望する通学区域内に両親に代わる保護者がおり、下校後の監護が適切に行われると認められる場合・・・勤務証明書、監護証明書
学区外就学を希望する際に、検討すべきポイント
学区外の小学校に通うとなると、事情によっていろいろなメリット・デメリットが生じます。では、「学区外就学をすべきか」「学区外のどの小学校を選ぶか」を決める際に、何をポイントに考えればいいのでしょうか?
通学距離
希望する小学校までの通学距離は、子どもが徒歩で無理なく通える距離でしょうか。また、学校までの道のりは、交通量の多い道路や危険な道を通らずに通えるかも重要かもしれません。公共交通機関を利用する場合も、無理なく安全に通えるかを確認するとよいでしょう。
利便性
学童保育の有無や、引っ越しなど家庭の事情に合わせることができます。一時の利便性のみを考えるのではなく、子どもが小学校を卒業するまで、また、中学校の学区などを考慮し学区変更を検討するとよいでしょう。
地域コミュニティとの関わり
通う学校が遠くなると、地域コミュニティとの関わりが希薄になる可能性があります。小学校の友達と遊ぶ場合も、自分だけ遠くまで遊びに行かなければならないという場合もあるかもしれません。
地域の催しや、お祭りなどに参加し地域コミュニティの中でも関わりを持てる機会を作れるように意識するとよいですね。
教育方針の選択
特に学校選択制で小学校を選ぶ場合は、子どもに合った教育方針の学校を選ぶことができます。希望する小学校の校風が子どもに合うか、在学している子どものママたちにどのような校風か聞いてもよいでしょう。
学区外就学は自治体に確認を

milatas/Shutterstock.com
今回の記事では、そもそも学区や通う学校はどのように決められているのか、また学区を変更して学区外の小学校に通うことはできるのか、学校変更の理由や申請方法、申請書・証明書などの必要書類についてもご紹介しました。自治体や、希望する理由に応じて学区外就学を認められる場合と認められない場合があるようです。学区外就学を検討する場合は、お住まいの自治体に確認してみましょう。通う学校の変更を検討するときは、小学校を卒業したあとの学区のことなども踏まえて、慎重に判断すると良さそうですね。











































































小学校入学前に引っ越しが決まっていて、通学区域外の小学校への通学をしたい旨の申請書を提出しました。引っ越し先の住所は学区内になるため受理されました。