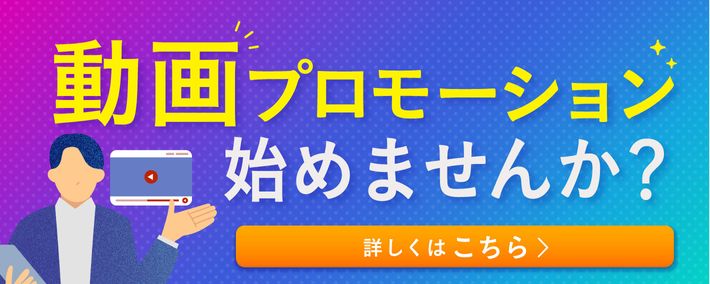こちらの記事も読まれています

勉強でラクをしようと思ってはいけない。とにかくやり続けることが近道ーー岸谷蘭丸の勉強法
名門私立中学を中退し、アメリカの高校に入学、現在はイタリアのボッコーニ大学在学という異色の経歴を持つ岸谷蘭丸さん。「幼少期は勉強が嫌で泣いていた」という岸谷さんですが、一方で「中学受験は絶対にすべき」と語ります。その理由とは?日本・海外の両方で数々の受験を経験した岸谷さんならではの勉強法に迫ります。

岸谷蘭丸。2001年7月7日生まれ、東京都出身。俳優の岸谷五郎と歌手で元プリンセス プリンセスの岸谷香の長男。現在はイタリアのボッコーニ大学に通いながら、海外大学・大学院の受験専門塾「MMBH留学」を運営する実業家として活躍。
海外留学はネガティブな理由がきっかけだった
ーー世界大学ランキングでトップ10に選ばれたこともあるイタリアのボッコーニ大学に通う岸谷蘭丸さん。まずは学歴について簡単に教えてください。
岸谷:小学校受験をして目黒にあるトキワ松学園に入学し、中学受験をして早稲田実業中等部に入学しました。ただ、高校に入るタイミングで早稲田実業は中退しました。その後ニューヨークの高校を経て大学受験で一浪。現在はイタリアのボッコーニ大学に通っています。

maccc-stock.adobe.com/jp
ーー早稲田実業学校中等部は難関校として知られる名門中学校の1つです。なぜ中退したのですか?
岸谷:端的に言うと、校風が合わなかったからです。早稲田実業には、友達がたくさんいたし楽しいこともたくさんありましたが、僕が嫌なものもたくさんありました。たとえば、「スポーツ」「厳しい校則」「質実剛健」、「去華就実」……。あと学校が遠すぎるのも嫌でたまりませんでした。
どうしても学校の環境が受け入れられなかったので、反抗心もあって中学3年間はまったく勉強しなかったです(笑)。おかげで自分の頭がどんどん悪くなっていくように感じて、「このままではダメだ」と学校を辞める選択をしました。
ーーそこからなぜ海外の高校に進学することにしたのでしょうか?
理由は2つあります。1つ目は早稲田実業より偏差値の低い学校には行きたくなかったから。でも3年間勉強していなかったヤツが、早稲田実業よりも上のレベルの学校に行けるわけないじゃないですか。じゃあ海外なら「レベルが落ちた」という感覚にならずに済むのでは?と思ったんです。完全にネガティブな理由です。
2つ目は、全教科のなかで英語が1番苦手だったから。リアルにbe動詞もわからないレベルで英語が苦手で…。それなら海外に行って死ぬ気で勉強するべきだと思いました。

kazoka303030-stock.adobe.com/jp
勉強でラクをしない。とにかくやり続ける
ーー高校時代の勉強方法について教えてください。
高校時代は毎日15~16時間勉強していて、まさに「寝る間も惜しんでやる」を体現していましたね。朝7時半に寮監にたたき起こされてから、深夜2〜3時に寝るまで、食事や部活の時間を除くすべてを勉強にあてる、まるで刑務所のような生活でした(笑)。

Kittiphan-stock.adobe.com/jp
そんな日々の中で、自分が何より重視していたのは「規則性を見つける」ことです。ありがたいことに、僕は幼少期から受験を繰り返してきたこともあって、「この問題の出題意図は?」「どういうパターンで出てくるのか?」と考える癖が自然と身についていました。
僕にとっての高校生活のゴールは、良い成績を取ること。そのためには、テストや課題で高得点を取る必要がある。では今何をすべきか。英単語か、数学の演習か——。常に逆算しながら行動していたんですよね。
一番効果的だった勉強法は「ラクをしないこと」です。もともと頭が良いわけではなく、勉強に向いているタイプでもない。だからこそ、ひたすらやり続ける。それしかないという覚悟。気合いと根性。最終的に僕を支えたのはそれでした。
目的意識がないまま進学する日本の教育
ーー教育環境について、日本とアメリカの違いはなんでしょうか?
岸谷:いちばん大きな違いは、「やりたいことは何か?」という問いが、日本ではほとんど投げかけられないことですね。言い換えれば、多くの学生が学力順に偏差値の高い大学に進学しているだけ、という状態です。だからこそ、就職活動の時期になって突然「やりたいことがわからない」と戸惑う学生があふれてしまう。
一方、アメリカでは高校生のうちから「あなたは何がやりたいの?」という問いを繰り返し突きつけられます。もちろん、16歳前後でやりたいことなんて明確に持っている人は少ないし、自分が何者かなんて誰もわからない。だから最初は、とても苦しい。
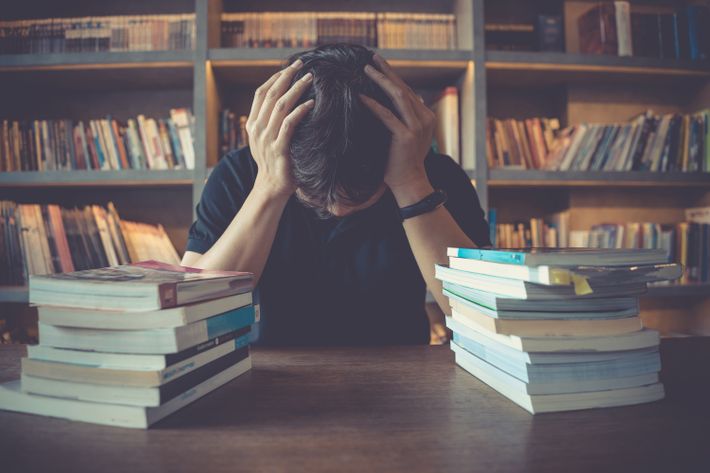
NopponPAT-stock.adobe.com/jp
それでも、「自分はどんな人間になりたいのか」「手放せない価値観は何か」「何が苦手なのか」と、日々自分と向き合い続ける。その結果、卒業する頃には自分の進みたい方向がある程度クリアになっている学生が多い。そして、「やりたいことを実現するために学ぶ」という視点で進路を選ぶからこそ、大学進学後の成長も大きいのです。
受験制度の違いも象徴的です。
日本では大学受験が“その一回”の勝負。高校生活でどれだけ努力しても、当日の試験で失敗すれば、それまでのすべてが無に帰してしまう。
対してアメリカの大学受験では、高校生活全体が評価の対象になります。筆記試験に加え、出席日数、課題の提出状況、授業への参加態度まで細かくスコア化される。つまり、「高校生活の努力そのもの」が評価される仕組みになっている。努力することにきちんとインセンティブがあるんです。
「死ぬほどコミットする」という経験が人生の財産になる
ーーこれからの時代、海外留学はマストでしょうか?

cassis-stock.adobe.com/jp
日本の教育について、つい悪い面ばかり話してしまいましたが、実は教育レベル自体はとても高いんです。国民のほとんど全員が字を読める社会なんて、海外では決して当たり前じゃない。そういう意味では、日本の基礎教育は世界的に見ても優れていると思います。
だからこそ、「日本人は全員、海外留学すべきだ」とまでは思いません。留学は、あくまで手段の一つにすぎないので。
本当に大事なのは、できるだけ早い段階で「自分にとって絶対に譲れないもの」を見つけること。
そして、それに対して本気で、命がけでコミットするという経験。限界を超えるような挑戦こそが、その後の人生にとって大きな意味を持つと僕は考えています。
そういう意味では、「受験」もまた、自分を試す手段になりうる。大切なのは、そのプロセスの中で何を得たか、どこまで自分を突き詰められたかだと思います。
ーー最後に、今まさに受験を考えている保護者、子どもたちに向けてメッセージをお願いします。
僕自身、幼い頃は勉強が大の苦手で、塾や家庭教師もとにかく嫌いでした。
でも今振り返ってみると、あの頃に身につけた勉強の習慣や考え方が、今の自分を支えてくれていると感じる場面がたくさんあるんです。

mojo_cp-stock.adobe.com/jp
だからこそ、どれだけ嫌がられても、受験という経験はやらせたほうがいい。そう思います。
もちろん、誰もが麻布や開成を目指すべきという話ではありません。子どものレベルや希望に合った学校を選ぶことが大前提。そのうえで、しっかりと努力を積み重ねることが大切なんです。
受験勉強は、子どもにとっても親にとっても正直苦しい。それでも親子共に「中学受験をやっていて本当によかった」と思う瞬間は、人生の中で何度も訪れます。僕の場合、それこそ100万回あったと言っても大げさじゃない。
いつか必ず、「あのとき頑張ってよかった」と思える日が来る。だから今は、とにかくやりきってほしい。親子で必死に頑張ったその経験が、きっとこれからの人生を強く支えてくれるはずです。