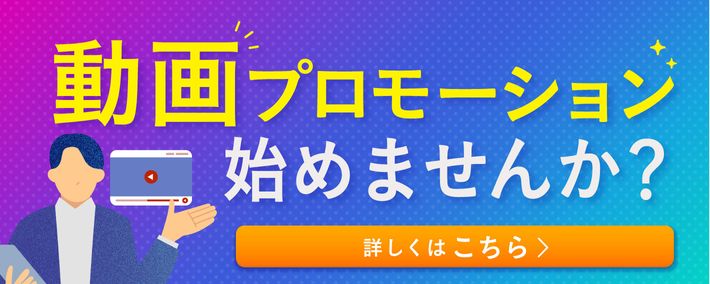こちらの記事も読まれています

「受験は二択。合格するか死ぬか」ドラゴン細井の勉強法
千葉大学・医学部を卒業後、美容外科医として活躍する一方、医学部受験塾MEDUCATEの塾長も務めているドラゴン細井さん。「令和の虎」シリーズをはじめとするSNSでの発言は、その歯に衣着せぬ辛口なトークが度々注目を集めています。今回はそんなドラゴン細井さんの勉強法に迫ります。

ドラゴン細井。渋谷幕張高校、千葉大学医学部卒。形成外科・美容外科医。渋谷アマソラクリニック院長。医学部受験塾MEDUCATE塾長。現役医師でありながら、受験界でも活躍。「最小の時間で最大の効果を手に入れる」ための効率的な学習プログラムは受験生だけでなくビジネスマンにもニーズが高い。登録者148万人超の『令和の虎CHANNEL』では投資側の審査員としても活躍。
勉強のために”半強制的”な環境を作った
--細井さんが医者を目指したきっかけを教えてください。
細井:僕の両親は医者ではなく普通のサラリーマンでしたが、親族に医者がいたこともあり、小さい頃から「医者は素晴らしい仕事だ」とずっと刷り込まれてきました。その影響で、自然と医者を目指すようになったのかもしれません。
そもそも受験勉強を楽しんで取り組んでいたら偏差値がどんどん上がっていったので、僕の中では「東大に行くか、医学部に行くか」の二択しかありませんでした。東大に行けば将来の職業選択の幅は残りますが、医学部に進めば医者になる道しかありません。そんな中であえて医学部を選んだのは、やはり医者という仕事に魅力を感じていたからだと思います。

tkyszk- stock.adobe.com/jp
――学生時代の勉強方法について教えてください。
細井:僕は偏差値を上げることが楽しかったし、受験戦争は苦ではありませんでした。ただ、どうしても勉強をしていて飽きる瞬間はあります。そのときは冗談ではなく、本当にベルトで椅子に自分の身体をしばりつけて、立ち上がりにくい環境を作っていました。
あとは、部屋のドアの前にソファーを置いて部屋から出られなくしたり。部屋から出てしまうと時間がもったいないので。小さいときからずっと勉強をしてきた人と違って、僕は受験勉強に打ち込んだのは2年弱だったので、自分を拘束して半強制的にやっていました。
――なぜそんなに自分を律していられるのでしょうか?
細井:受かるか死ぬかで、その二択以外ないと思っていましたから。受験生に社会的意義はないから、合格するか死ぬかしかないんです。All or nothingです。だからこそ、机に向かうしかない状況を自分で作るんです。たとえば「立った瞬間にピストルが発砲される」くらいの強制力をイメージする感じです。
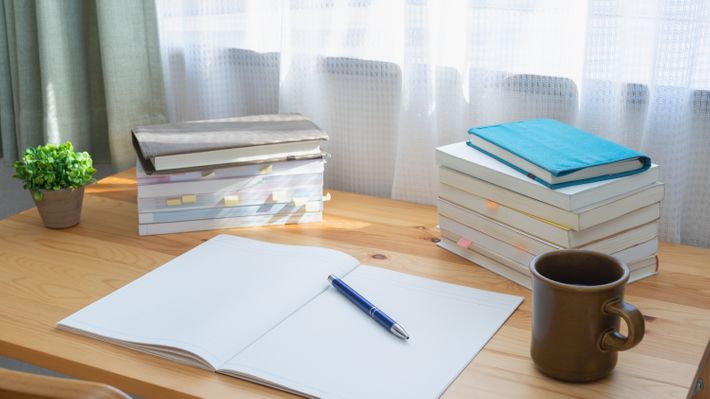
aomas- stock.adobe.com/jp
目標は死ぬ気で達成すべき
――受かる人と受からない人の差はどこにあると思いますか?
細井:普通にやる気の問題だと思いますよ。単純に甘ったれているから、自分で言ったことを守れない。自分で「受かるか死ぬか」と決めたのなら、死にたくないから受かる。ただそれだけ。勉強の手法というのは、この時代にすべて情報が落ちているし、無料で手に入ります。なので、やるかやらないかだけの違いです。
ただ、先ほど話した自分を椅子に縛り付ける方法もそうですが、形だけ真似するのでは意味がありません。根本にあるのはマインドです。マインドがあるから、自然とそのような行動につながる。
一方で、まずは形を真似するのもけっこう大事で「TTP」とよく言いますが、徹底的にパクる。よくスポーツを始めるときにウェアからそろえる人もいますが、形からマインドをそろえていく方法もあるとは思いますね。
――細井さんが経営している医学部専門塾で、生徒にもっとも伝えていることはなんですか?
細井:医者にならないやつはゴミだ、と言っています。もちろん医者になりたい人に対してだからそう言っているだけで、医者以外の仕事をゴミだなんて思っていないですよ。ただ、いま医学部を目指していてそれを達成できていないのなら、残念ながら現状はゴミだし、目標を達成してはじめて人間になれるということです。
両親からは異常な愛を受け取った

buritora- stock.adobe.com/jp
――細井さんが育った家庭はどんな環境だったんですか?
細井:父親は航空会社で、母親はテレビ関係の仕事で、ふたりとも会社員でした。そこまでボンボンという感じではなく、ごく普通の収入の一般家庭です。うちの親は、自分たちが学生の頃にお金がなかったり兄弟が多かったりで、思うように勉強をさせてもらえなかったというコンプレックスがあって、そのコンプレックスを幼少期の僕にパイ投げのように盛大にぶつけてくれました。それは異常なくらいの愛だったと思います。
あまりに大きい愛をぶつけられてつぶれてしまう子もいると思うので、愛のぶつけ方はとても大事ですが、僕にはその愛がしっかり伝わってきました。もちろん死ぬほど反抗して言うことを聞かない時期もありましたが、その愛を根本的に受け取っているから、椅子にベルトを結んで自分で律することができたんだと思います。
いま自分が受験教育に携わっていると、親がそこまで子どもの勉強に介入してくれたのは、かなり大変なことだったんだなと思います。うちはお金持ちでもなければ、一人っ子でもなかったのに、あれだけのお金と労力をかけてくれたのは本当にすごいと改めて感じています。
受験生は寝るか勉強するかの二択
――受験勉強中のスケジュールを教えてください。

tippapatt- stock.adobe.com/jp
細井:寝るか、勉強するかの二択です。これは塾の生徒にも話していますが、ご飯、お風呂、トイレ、移動のすべてを勉強時間にあてることが、必勝パターンです。普通はこれらの時間をどう頑張って削っても、1日に3~4時間は取られてしまいます。
だから、風呂場には風呂場用の教材を、トイレにはトイレ用の教材を、移動には移動用の教材をそれぞれ用意すること。睡眠時間は最低でも6時間は確保したほうがよいです。昼寝も効率的に取るのはOKです。
そもそも受験生に自分の時間は必要ありません。受験生はしっかり勉強をして、大学に合格して、社会的に一人前になって旅立っていくのが仕事なので、娯楽や生活の楽しみは必要ありません。現役高校生の場合はもちろん学校もあるし、友だち付き合いもあると思います。でも、受験戦争に勝ちたいと思うのであれば、休み時間も自習室に行って勉強するのは鉄則です。
やった気になるのが一番NG
――勉強は質も大事だと思いますが、質を上げるにはどのような工夫がありますか?
細井:量をしっかりやってから質が上がってくるものなので、まずは量を意識してやってほしいですね。あとは、科学的な根拠に基づいた復習のタイミングはとても大事だと思います。たとえば「忘却曲線」は誰でも聞いたことがあると思いますが、実践できている人はかなり少ないです。

Abdul- stock.adobe.com/jp
だから「どうしたら実践できるか」を考えることが大事です。今はアプリで勉強を管理したりする方法もありますよね。うちの塾では、2週間単位の勉強予定表を作っていて、必ず寝る前に1週間前にやった内容を復習するスケジュールになっています。このような方法でより科学的に、脳に染みこませる勉強を心がけてみてはいかがでしょうか。
一方で、やった気になるのが一番よくないです。たとえば単語帳は、見た瞬間にスラスラと言えてはじめて覚えたと言えるのに、そのレベルになっていないのにやった気になっている人が多すぎます。つまり、自分で学習をチェックする能力が破綻しているんです。
それでは話にならないので、僕の塾に来るなり何かしらの方法で、第三者のチェック機能を使わないと危険です。これって医者になってからも大事なことで、あらゆる業務でダブルチェックは必要ですよね。自分が完璧にできないのであれば必ず第三者にチェックしてもらうというのは、受験勉強も同じだと思います。
デジタル管理が適当な場面もある
――細井さんが努力を継続できるのはなぜですか?
細井:努力を努力だと思ってないからですね。他の人たちがサボりすぎ、やる気なさすぎだと思います。死んだらいくらでもグダグダできるのに、なんで生きている間に頑張らないんですか、と。寝る時間だってあるんだから、起きている時間くらいは何か一生懸命やったらいいのに。人生80年くらい走り続けたって何の問題もありません。そのあとずっと寝られるんだから。
――勉強において現代だからこそ大事なことを教えてください。
細井:スマホアプリをうまく使うこと。スマホは諸刃の剣ではありますが、親がしっかり管理をすれば勉強にも最強のツールです。なかにはエンタメの要素もかなり多いので、そこをうまく排除しながら使うこと。
アナログよりもデジタルで管理するほうが、勉強量や復習のタイミングがわかったり、全てにおいて効率的に管理できますから。子どもにスマホを与えるときに、そういったプラスの面だけを与えて、マイナスの面を排除できるような渡し方を心がけるとよいと思います。

buritora- stock.adobe.com/jp
うちの子どもはまだ小さいのでそのようなアプリは使っていませんが、通っているインターナショナルスクールでは、ゲームをうまく使いながら学習を進めるようなツールが色々あります。子どもにはゲームをしたい欲求が絶対に生じてしまうので、それをテレビゲームではなく勉強に紐づくゲームをすることでその欲求を緩和しつつ勉強につなげる、ハイブリッドされたよい策だと思います。
でも、最終的に試験問題を解くのは自分の手と鉛筆。そこは何十年も変わっていないので、あくまでデジタルは補助的なツールとして使うとよいですね。