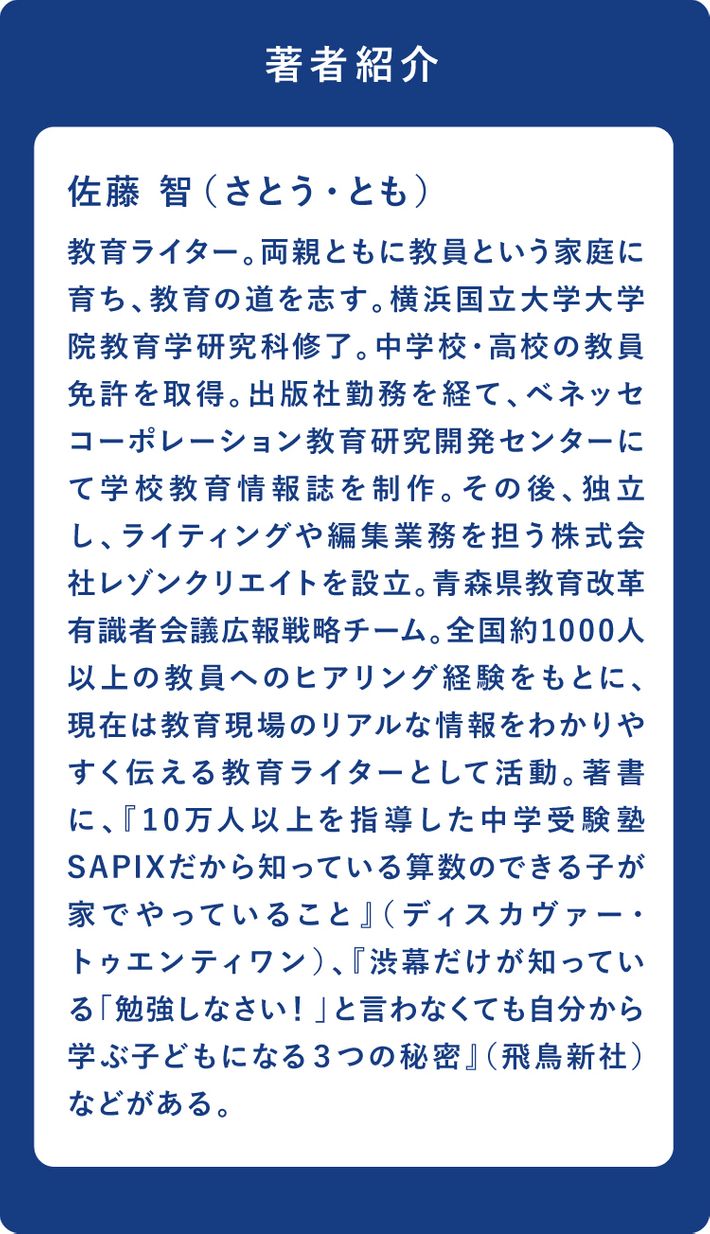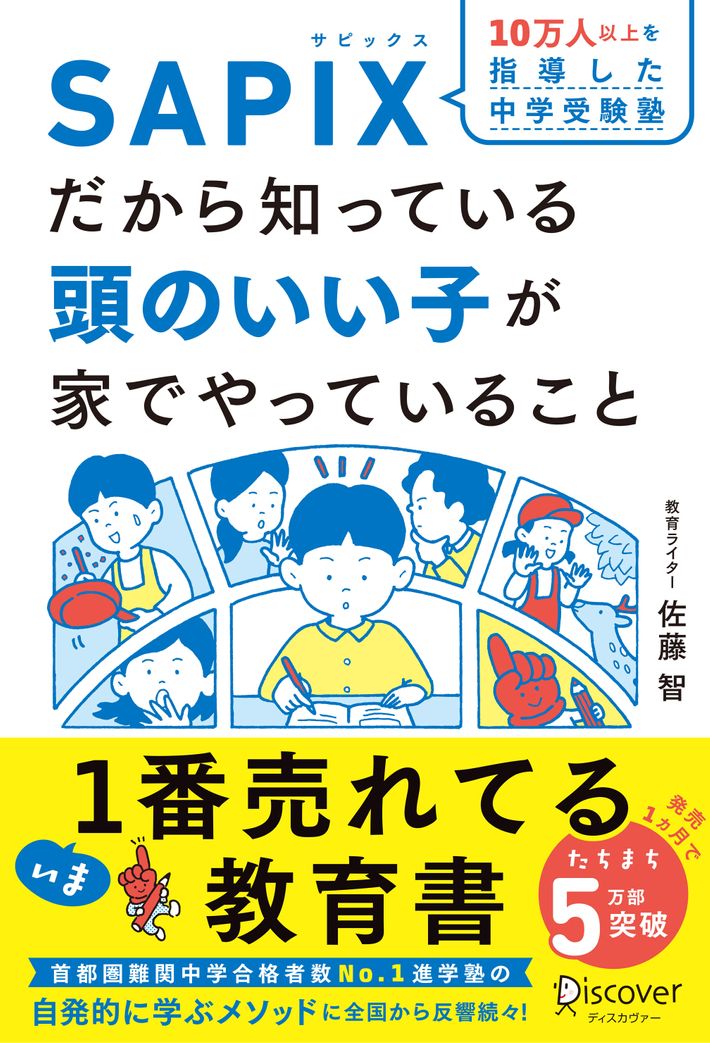こちらの記事も読まれています

SAPIXだからわかる「頭のいい子」の本当の意味。算数ができる子は不正解を楽しめる?
KIDSNA STYLE編集部が選ぶ、子育てや教育に関する話題の書籍。今回は、『SAPIXだから知っている 頭のいい子が家でやっていること』(佐藤智/ディスカヴァー・トゥエンティワン)をピックアップ。学びが楽しくなり、自発的に勉強をはじめ、自然と学力につながっていく。そんな子を育てるために家庭でできることを、教科ごとに解説した一冊です。

「頭のいい子」とはどんな子?
「頭のいい子」というと、どのようなイメージを持ちますか? 成績のいい子? なんでもパッと理解ができる子? 大人っぽい子? そのどれも間違いではないですが、私は「学びに関心を持ち、学び続けられる子」だと考えています。
先行き不透明なこれからの時代は、学校や塾で何かを学んで、それで「おわり」ではありません。知識を頭に入れたそばから、どんどん新たな情報にアップデートされていきます。大人になったら学ばなくていい、なんてことは絶対にありえません。これからは、どんな生き方を選んでも「学び続ける姿勢」が求められます。
そして、学び続けるエンジンになるのは、好奇心や興味関心、探究心です。「もっと知りたい」「これはどうなっているんだろう?」そんな意欲や疑問が背中を押して、自らすすんで学ぶ子が育っていきます。
子どもたちは生まれながらにして、 好奇心や興味関心、探究心をもっています。そして、それらは多様な体験から一層育まれていきます。お金をかける必要はありません。遊びのなかで、家庭の会話で、お手伝いで、旅行やイベントごとで……。子どもを取り巻くありとあらゆる環境がそれらの機会になるのです。
叱るだけでは子どもは伸びない
子どもが勉強に向かっていない姿を見て、焦る保護者も少なくありません。しかし、学びとはドリルを解いたり教科書を読んだりすることだけではありません。生活の中から子どもはたくさんのことを学んでいる。その姿をよく観察し、少しでも深く考えたりその子なりの発見をしていたりしていたら、「おもしろね!」「よく気付いた!」とお父さんお母さんに褒めてもらいたいのです。
そもそも100点満点のテストで30点しか取れなかったことを責めても、子どもは問題を解けるようにはなりません。「自分は勉強ができないんだな」「怒られるからやりたくない」という気持ちしか残らないのです。大事なことは、「ここはできているね」「この問題はこんなふうに考えたんだね」とプロセスを認めること。そして、前向きな気持ちで、「次はこうしてみよう」と思えるようになること。責めたり叱ったりすることで、学びへの積極性は生まれません。
もし、叱られることで勉強するようになったと感じることがあれば、「次は叱られないようにがんばろう」という受動的な気持ちによるものです。叱られないように勉強している場合でも、ある程度のレベルにまで達する子もいるかもしれません。しかし、「学ぶことが楽しい」という気持ちが根元に育っていないため、学び続けていく姿勢にはつながりにくいのです。
国語が伸び悩めば他教科にも響く
国語は全教科の基礎となる教科です。教科の学びにおいては、活字から解釈していく、それを説明していくという力が問われているからです。だからこそ、大切なことは苦手意識を持たせないことだといえます。
ときに、「うちの子、読書が苦手で」といった言葉を耳にすることがあります。「勉強しなさい!」という指導と同様に「本を読みなさい!」と伝えても、本人がおもしろいと思っていない場合には、なかなか効果が出にくいものです。まずは保護者が本を読んで、楽しんでいる姿を見せること。本が身近にある生活をしていくことが鍵となります。
一方で、読書が好きな子に対して「読書はやめて、勉強しなさい!」と言うことは、国語力の伸びとともに、他の教科の伸びも頭打ちになってしまう可能性があります。本好きの心を大切にしてあげてください。
高学年頃になると、お父さんお母さんと同じレベルの本を読めるようになる子もいます。大人の視点に触れることも重要な体験なので、「このエッセイおもしろかったよ」など視野が広がるような本を子どもに手渡してみるのもよいでしょう。
また、「国語はできるんだから、他の教科を勉強しなさい」などと止めないことも大切です。
算数ができる子は不正解を楽しめる
算数が得意というと、天才的なひらめきを持っている子をイメージするかもしれませんが、決してそれだけではありません。ゲーム感覚で楽しめる子は算数を楽しんで解けるようになる傾向があります。失敗を恐れるのではなく、「間違えたらもう一回やってみよう」と思える子は、算数が得意になることが多いのです。
また、 「ゲーム」だととらえると、算数の問題に対して「なんでこういうルールになるの?」「こんな状態、絶対に起きないじゃん」といったことに子どもが引っ掛かりにくくなります。たとえば、「分数の割り算は、なんでひっくり返して掛け算するのか?」という子どもの疑問があったとします。こうした子どもの問いは、学びの原点なので大切です。ただ、算数を解いていくにあたっては一旦横に置いておくことが必要なこともある。その場合には、「ひっくり返して掛け算することはゲームでいうルールだ」という理解が求められます。
他にも、「時速60キロで3時間進みました」といった文章題があるときに、「その速さで走れるわけないでしょ」「ずっと同じ速度のはずないよね」などと引っかかってしまうと、問題を解く手が止まってしまいます。「こんなことあるわけないじゃん」とどこかで思っていたとしても、「ゲームだし」「こういうルールなんだな」と客観的に見られると、すんなり取りかかることができるようになります。
社会こそ親子でフィールドワークを
社会科はまさに「社会」を学ぶ教科です。大人の中には、自身の受験勉強のイメージが強く単なる暗記教科という意識を持っている方もいますが、そこから抜け出すことが重要です。子どもの興味を育んでいくためには、地図帳や地球儀、歴史漫画などの社会科に触れる要素を散りばめていくこと。また、どんどん「外」に出て身のまわりの気付きや疑問を拾い上げていきましょう。
たとえば、自宅近くをお散歩してみるのはいかがでしょうか。坂道や川、池など地形の違いに注目してみてください。坂が多い地域では、なぜこんなに坂が多いのかを子どもと一緒に考えてみる。川が流れている地域では、どこから流れてきてどこに向かっているのか、川のまわりはどうなっているのか観察してみるのもいいでしょう。
旅行も気付きや発見の宝庫です。山の中を車で走り、トンネルを越えると天気が変わっていることがあるかもしれません。そんなとき、「なんで天気が変わったんだろう」と子どもと一緒に考えてみてください。神社仏閣を訪れたら、マナーやその意味を考えてみるのもいいですね。
こうした気付きや疑問に対して、子どもは「授業でこう習ったよ!」と話してくれるかもしれません。知識がなければ「調べてみる!」と行動に移したり、「もしかしたらこうかも」と仮説を立てたりするはずです。このようなひとつひとつの貴重な体験が、社会科の学びにつながっていくのです。ぜひ、外へ遊びに出かけてみてください。
中学入試の理科では料理も問われる
最近ではキッチンに立ったことがない子が増えてきました。子どもの仕事は勉強と遊びだけと決めてしまって、お手伝いをする時間が減っているのかもしれません。料理を手伝う機会がないと、キッチンに置いてあるものに触れることがないままになってしまいます。たとえば「みりん」は何に使うもので、どんな味がして、調理に使うとどのような効果があるのか。料理をしていれば身に付くことも、現代の子どもたちは知る機会が少なくなっています。
お手伝いにはたくさんの学びがありますが、そのなかでも料理は、生物や化学の分野と非常に深い関わりがあります。そのため、料理は理科に興味をもったり知識を広げたりするのにうってつけの体験です。また、中学入試においても料理の問題は頻出します。
鮭の切り身が、鮭全体のどの部位にあたるのかを問う問題、調理後の野菜とスーパーで販売されている加工前の野菜とを紐づける問題、旬の食材を答える問題など、多様な出題がなされます。加工や調理済みの状態しか見たことがない子どもは、こうした問題を難しく感じてしまいます。
毎日でなくてもいいので、月に2回は料理デーにしてみたり、一緒にスーパーに行ってみたり。家事をイベント化することで、子どもは特別感を覚え、忘れがたい経験になることでしょう。