こちらの記事も読まれています

子どもに対し愛があるだけでは足りない。狂気をデザインする子育てとは
現役医師でありながら医学部受験塾の塾長も務める勉強のプロであるドラゴン細井さんと、イタリアの難関ボッコーニ大学の現役生でもあり、海外大学受験サポートの会社を経営する企業家である岸谷蘭丸さんが、未就学児〜小学生の子どもを持つKIDSNAアンバサダーのお悩みに答える企画。進行は、2児の母でもあるタレントの鉢嶺杏奈さん。前編のテーマは、お金と愛のどちらが大事か。
親は「愛」だけではなく「狂気」を持つべき
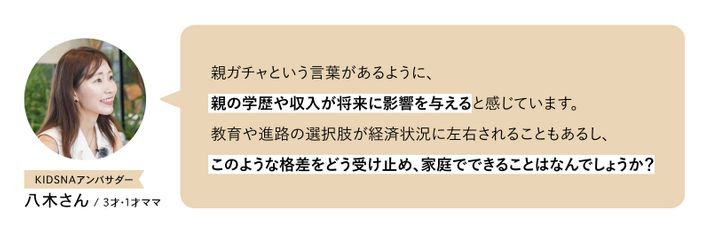
細井:八木さんは学歴が高いですか?
八木:普通くらいです。
細井:なるほど。まず、子どもに対して申し訳なく思っているのだとしたら、その考え方が間違っています。申し訳なく思う前に、できることはたくさんある。収入はあなたと旦那さんの努力でどうにでもできますよ。また、親に学歴がなくても「教育力」さえあれば、子どもは優秀に育つのです。たとえば親が教師の場合、学歴がそんなに高くなくても、子どもの学歴は高くなる傾向があります。つまり、学歴と教育力はイコールではありません。
実際に東京大学の生徒の親がみんなお金持ちか高学歴かというと、実はあまり関係がなくて、一般家庭の方もいくらでもいます。もちろん大枠で見たら平均年収の隔たりはあると思いますが、例外は存在しますし、その例外を僕たちはたくさん知っています。子どもの教育に親は絶対に必要だし、親が学歴や収入に自信がなかったら、お子さんと一緒にレベルアップしていけばよいのです。
岸谷:完全に同意です。
鉢嶺:納得のいく意見ではありますが、親も大変で…。習い事だって親の経済状況によってやらせてあげられないこともあるし、その分引け目を感じてしまったりはしますよね。
細井:お金より愛が大切です!僕はお金をかけてもらって不自由なく育った側ではありますが、お金があるから全員幸せなわけではないですよね。親から愛情をかけてもらったかそうでないかは、後からどうしようもない部分です。結局親が愛してあげて、自分に価値があると疑わないくらい自分で自分を愛することができることが、人生においていちばん幸せだと思います。

ドラゴン細井さん
岸谷:そうですね。お金も愛も両方あるのが理想ですが、お金よりは愛が大事だと思います。
細井:そして、愛に勝るものは「狂気」です。お母さんたちはみんな子どもに対する愛を持っていて、特にこのメディアを見てる人は大きな愛を持っている人だと思います。だとしたら、周りの母親と同じでいいのかと。愛を超えて狂気まで昇華させないと。この世界で勝てる子どもを育てるためには、親としても頭ひとつ飛び抜けないといけません。
子どもは親のコンプレックスをぶつける対象ではないですが、自分が辛い思いをしたことがあるのなら、それを子どもに味わってほしくはないですよね? 自分が小さい頃にしてほしかったことを、より改善してお子さんにはプレゼントしてあげたいですよね? それをするには、愛では足りなくて、自分の枠組みを超えていくような狂気が必要なんです。
幼少期からの取捨選択の必要性
鉢嶺:でも、そこまで子どもに手をかけすぎると、子どもが失敗を学べなかったり、マイナスなこともありそうです。
細井:例えばですが、受験勉強、英語、3つの習い事を毎日やっている子がいたとします。そのすべてがハイレベルにこなせると思います?
鉢嶺:どれも中途半端になりそうですね…。

鉢嶺杏奈さん
細井:確実に中途半端になりますよね。ですが、世の中のお母さんたちは、これをやりがちです。なぜかというと「この子には何が合うかわからないから」と言うのです。でも、一日中子どもと一緒に過ごしていて、何が合っているかは見抜けないんですか? たとえば3歳くらいの子が体操教室でやっている内容は公園でもやらせてあげられるし、初歩のピアノは家でもできる。それをせずに、習い事に行かせて満足させている親の多いこと。
愛をお金と勘違いしているんです。習い事をたくさんさせたり、小1からSAPIXに行かせることが愛だと勘違いしている。小学校低学年の勉強なんて大人は誰でもできるのに、なぜ塾や習い事に行かせる必要があるのでしょうか。
鉢嶺:でも、習い事は挨拶の仕方を学んだり、人との関わりを広げたり、毎週そこに行く習慣とか、いろいろ身につけられることもあるじゃないですか。
細井:人生で勝ちにいきたいのであれば、幼少期からの取捨選択はとても大事です。まんべんなく色々なことをやってみて、「これはできたね」「これはできなかったね」というのは、時間がもったいないです。
僕は、余計なスポーツや習い事をしなかったのがよかったと思っています。時間は限られてますから。中学受験である程度よい中学に受かりたかったら、5,000時間とか勉強しないといけないので、サッカーや野球とか習い事でスケジュールを埋められたら大変ですよ。どう考えてもこの体格で大谷翔平になることはできないので、無駄。
そもそも世の中にある職業のなかで高収入を手に入れるには、プロスポーツ選手を目指すより、学歴をつけるほうが確率が高いじゃないですか。運動神経も大事ですが、それは中学・高校に行ってからやったらいいですよ。
子どもの横で親も勉強するのは極めて当たり前
鉢嶺:蘭丸さんはどのように育てられたのでしょうか?
岸谷:僕は体操、ピアノ、水泳、受験塾、テニス、ありとあらゆるものを全部やってきました。

岸谷蘭丸さん
細井:やったんかい(笑)!
岸谷:僕は習い事は楽しかったのでよかったです。結果何かに繋がったわけではないですが、やってよかったとは思います。
細井:正直、蘭丸は親ガチャを引いているから、何やっててもオッケーではある。持っている者と持たざる者がいるのは現実なので。自分は普通のサラリーマンの家庭だったので、親は狂気を持って接してくれました。
でも、狂気といってもやり方はたくさんあって、時代も変わるし、お子さんの特性もある。要するに愛の伝え方をどうデザインするか。狂気といっても色々な色があるし、一言では言えません。でもそれくらい親が躍起になってほしいということです。
例えば、塾の送り迎えが大変で疲れると言いますが、ちゃんと運動して体力をつけていますか? 子どもに運動を教えるのに親が運動できないというのもありえない。僕は極真空手の稽古に週3回行きますよ。それくらい自分を高める意識を持っていないと、子どもには伝わりません。子どもが勉強をするときには親も隣でやりなさいとよく言うじゃないですか。これは本当にやって当然ですよ。
鉢嶺:ちなみにドラゴン先生はご両親からどのような教育を受けたのでしょうか?
細井:もうイかれてましたよ(笑)。でも、僕が3〜4歳の頃、勉強をするのが嫌で全然言うことを聞かなかったときに、親は見えないところで泣いていたのを今でも覚えていて。泣くくらい教育に一生懸命だったんです。僕が医学部に入ってハングリー精神を持って今も生きているのは、親からもらったそういう想いがあるから。
12歳までに地頭や思考力を育てる
八木:私は子どもの頃、習い事の練習をしなかったり、テストの点数が悪かったりすると親から怒られて、手を出されていたんです。頑張っても褒めてくれないし、それがすごく嫌でした。どうやって休もうかな、どうやったら怒られないかなと、そればかり考えていて。そして、努力しても報われないからやめようと思っちゃったんです。
細井:それで、自分が親になったときに、子どもに対して申し訳なさを感じるようになってしまったんですね。自分がデザインされた狂気をもらっていないから、子どもに対してもデザインできない。自分みたいに挫折しちゃうんじゃないかという恐怖心がありますよね。だからこそ、叱り方や伝え方をプロから学んだり、自分自身が教育を勉強しないといけないんです。
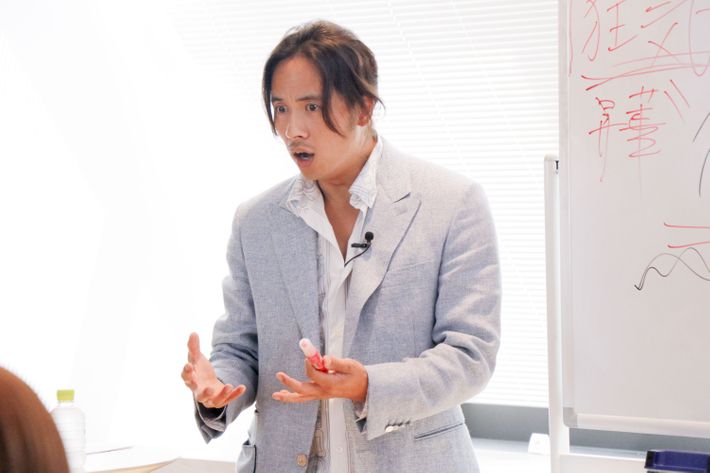
ドラゴン細井さん
岸谷:僕も思い返すとプレッシャーはありました。親に怒られるとかではなく、周りの目のプレッシャー。僕が失敗すると「やはり二世。岸谷の息子はやっぱりだめだ」となってしまうので、失敗できない、勝たないといけない、という想いはずっとありました。
僕は、地頭や思考力、瞬発力や馬力みたいなものは、12歳くらいで天井が見えてしまうと思っていて。それ以降はどんなにやらせても上がらない。だから、小学校・中学校までに伸ばしてもらったことって、すごく大事なんです。その時期にプレッシャーを与えてもらって、伸ばしてもらったことは、人生で必ず活きるので。社会に出てから周りの人を見ていても、中学校受験を頑張った人は力があると実感します。
優秀な人たちはよく「大学はあまり関係なくて、中学・高校が大事」と言います。12歳くらいまでにほとんど決まっちゃうから、そこまでにどれだけ頭を使ったか。中学受験をやらずに飛ばすのは、すごくマイナスだと思います。僕は幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、全て受験しています。
細井:これはご両親の素晴らしい教育プランですよね。小学校受験だけで怠けさせない。幼稚園で慶応に行かせて、そのまま大学まで、とか考える人と大きく違うと思いますね。



































































