こちらの記事も読まれています

「勉強しなさい」は言わない、授業は教えない。子どもの自己決定を見守る子育て
KIDSNA STYLE編集部が選ぶ、子育てや教育に関する話題の最新書籍。今回は、『「勉強しなさい!」と言わない子育て 学ぶ力の育て方』(時事通信社)を一部抜粋・再構成してご紹介します。横浜創英中学・高等学校副校長で「教えない授業」を実践する著者・山本崇雄氏が、子どもの可能性を信じ、温かく見守る子育ての秘訣を伝えます。

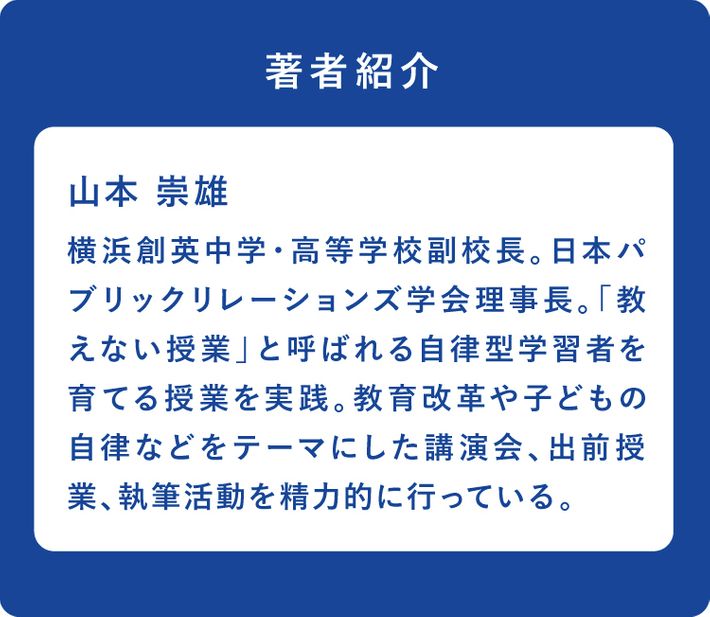
変わりつつある令和の学び
学校教育が「指示待ち人間」をうみだした
Q:会社では「指示待ち人間」の多さが話題になっていると感じます。原因はどこにあるのでしょうか?
A:学校教育が子どもたちにサービスを与えていくものになってしまい、そのツケが回ってきたというところでしょうか。よい大学・よい会社に就職して終身雇用が約束されていた時代とは違うのにもかかわらず、子どもたちの主体性を育むような学びへの変化が起こらなかったことが原因のひとつでしょう。
主体性を取り戻させるのは簡単なことではありません。親や周りの大人に頼りきりの幼稚園生を主体的にするには3カ月、小学校6年間を親や先生の言いなりに過ごした子を主体的に変えるには1年、中学卒業まで依存状態で過ごした子を高校で主体的にするには3年かかるとも言われています。
だからこそ、主体性を身に着けさせるのであれば、学校に通っている間に自ら学ぶ力を養い、取り戻させることが重要なのです。
大人に従うこと自体が悪いわけではない
Q:大人の言うことをよく聞く「従順な子ども」は、これからの社会ではダメなのでしょうか?
A:そんなことはありません。大切なのは「しなさい」と言われて「する」という判断をするのに、自分の意思があるかどうかです。目的や理由も考えずに、親や教師の言うことに従っている「だけ」では、主体性は育たないということです。
そのためには、子どものうちから「どうしたい?」と自分で考えることを促し、自分で判断し、動くことを繰り返させることが大切です。もちろん、間違った判断や行動をしてしまうことも多いと思います。でも、失敗したときに原因を考え、周囲にアドバイスを求める、助けを求めるということを覚えることも重要です。
それに、子どもの失敗は大人がカバーできることがほとんどです。親が子どもと過ごせる時間は考えているよりもずっと短いので、その時間を「〇〇しなさい」と言い続けるのか、子どもの自己決定を見守って応援するか。どちらがいいと思いますか?
学びの主人公は子ども 教えない授業のススメ

※写真はイメージ(gettyimages/Prostock-studio)
教えない授業とは……?
Q:教えない授業とはどのような授業なのでしょうか?
A:主体性を育む授業です。これまでの日本の教育では、一斉教授型といって、すべての子に同じ方法で同じペースで教えていました。でも、子どもによっては「難しすぎる」「簡単すぎる」「説明が速すぎる」といった問題が生まれていました。そうではなく、子どもたち一人ひとりの学力や学び方の個性に合わせるのが、僕の実践する「教えない授業」です。
「教えない授業」を行う学校の教室には、自分の学びのペースや興味に沿ってひとりで進める子もいれば、教師の説明を聞いている子もいるし、友だちと教えあって進める子もいる。いろいろな学び方をする生徒が混在しているのです。
子どもたちから「教えて」と言われたときには、いきなり答えを教えることはありませんが、調べ方は教えます。「〇〇について、先生の説明を聞きたい」と言われたら、クラスに対して「こういう質問がありました。説明を聞きたい人は前に集まってください」と呼びかけます。
また、さまざまな学びの手法を子どもたちに提供して、経験させています。AIを使った学習アプリやYouTubeも活用しますよ。
学びの環境を整えるのは大人の役割
Q:教えない授業で基礎学力は本当に身につきますか?
A:学校は教育課程を無視した教育活動を行うことはできませんから、その学年として必要な基礎学力を学ぶことは保証されています。ただ、教育の手法として、教師が一方的に教えるのではなく、生徒が主体的に学ぶ形を取っているだけです。
教育課程にある学年に応じた教科の学びが取りこぼされることがないよう、学びに関する情報をWeb上に整え、生徒がいつでもアクセスできるようにするなど、学びの環境を整えるのは教師の役目です。決して放任しているわけではありません。
子ども自身の「学びたい」を待つ
Q:「教えない授業」では、サボる子はいないのでしょうか?
A:「教えない授業」を取り入れた直後は、3割くらいの生徒が友だち同士でおしゃべりをしたり遊んだりして、教室はカオスです。ただ、そうした状態が続くのは大体はじめの2~3カ月です。1学期半ばには勝手な行動をとる生徒は数人程度に減り、その数人も大抵2学期には落ち着きます。
サボり続ける生徒に対しては、「勉強をしない選択をしてもいい。その権利が君にはある。ただ、誰かの学びを邪魔することは許さないよ」と伝えます。そして、「君はどんな学びをしたい?」「君がやりたいことのために、先生にできることはある?」と対話をしながら、子ども自身が「こうしたい」と言ってくるのを待ちます。
ただ、授業から離れてしまった生徒は、実は周囲の目を気にして不安になっているものです。子どもがどんな選択をしても見守り、応援していく対話を続けることで、学校や教師に対する信頼が育ち、やがて学びの場に戻ってきます。

※写真はイメージ(gettyimages/gyro)
学びを支える家庭の役割とは
「勉強しなさい」を言わない効果
Q:「勉強しなさい」と言うのは、やっぱり子どものやる気をそぐのでしょうか?
A:はい。親が「勉強しなさい」と言うのをやめるだけで、子どもはずいぶん気が楽になるものです。
そもそも家でそんなに勉強をしないといけないのでしょうか? もし学校で十分に頑張っているとしたら、家ではそれほど頑張らなくてもいいのではないでしょうか。家でだらだらする時間があってもいいと思います。もしかすると怠けているだけのように見えても、頭の片隅でなにか考えていたりするかもしれません。
家庭ルールなどでも、子どもの選択権を認めることは大切です。「学力はあるけれど、自分で何も決められない子」と「学力はちょっと心配だけど、自分で決めて行動できる子」では、後者を育てることを意識しましょう。
子どもが主体性を取り戻すとっておきの声がけ
Q:子どもの主体性に任せたいけれど、なかなか成長が見られないときはどうしたらよいでしょうか?
A:とっておきの言葉があります。なくした主体性を取り戻すには時間がかかるとお話しました。小学校6年間、先生や保護者の言いなりに過ごしたてきた中学一年生に主体性を取り戻させるには、一年のリハビリ期間が必要です。つまり、たとえば中学一年生の子が、スマホの利用時間について自分でコントロールできるようになるには、一年くらいかかるということ。
それをふまえて、「一年後には自分でスマホをコントロールできるようになっているだろうね。今はできないかもしれないけど、できるようになるのが楽しみだね」といったように、「少し先の未来がうまくいっているイメージが持てる言葉」をかけるのです。それによって、うまくいった自分を意識することができるようになります。
また、親が期待をしてくれると、その期待に沿った成果を出しやすくなるというピグマリオン効果もあります。子どもには、うまくいく未来につながる言葉を積極的にかけていきましょう。

※写真はイメージ(gettyimages/takasuu)
子どもが思春期に入る前のコミュニケーションを
Q:中学生の息子があまり会話をしてくれなくなりました。
A:反抗期という言葉もありますが、そういう態度を取りやすくなる時期だと覚悟しておきましょう。ただ、思春期の親子関係は難しいものなので、思春期に入る前からのコミュニケーションで、親に対する信頼や安心感を育んでおくことが大切です。
たとえば、公園で遊ばせておいて、自分はベンチでスマホを見ているのはよくないと思います。小さな子どもは遊んでいる最中でも、親や周囲の大人に視線を向けて、アイコンタクトを取ろうとします。そのときに親が自分を見てくれていないという悲しい経験が積み重なると、親は自分に関心がないんだという感情が育ってしまいます。
小さいときからのコミュニケーションによって、「親は自分がどんな選択をしても、ちゃんと話を聞いてくれる。受け止めてくれる」と、子どもが親を信じられるようにすることが大切です。
学び方・学ぶ環境の整え方
最後までやり遂げなくてもいい
Q:自分で決めたことは最後までやり遂げさせないといけないのでしょうか?
A:継続することにつまづきを感じたら方向転換を図るというのは、むしろ重要なスキルだと思います。これからの社会では、さまざまなことに興味を持ってスキルを身につけ、同時進行で複数のことに取り組む「マルチタスク」も重要となるはずです。大切なのは、続けるにしても、やめるにしても、本人が決めること。
終身雇用制度が変わってきているいま、得意分野は複数あったほうが、自分を生かせる場所の選択は増えてくると思います。ひとつのことを極めるのも素晴らしいけれど、知識や技能は必要に応じて後から高めることもできる。だからこそ、やりたいことはひとつに絞らなくてもいいし、いろいろなことに興味関心を持って挑戦できることが大切です。
やる気が出なくても勉強する準備は整えておく
Q:家で勉強するときに集中できないし、やる気も出ない場合はどうしたらよいですか?
A:やる気になれなくても、とりあえず勉強道具を整えて、机の前に座ってみることです。そして、音読などの取り組みやすいことから始める。とにかく行動をしてしまえば、脳は活性化するからです。
また、スマホやタブレットが手元にあると勉強に集中できないから、電源を切ったり違う部屋に置いている子も多いと思います。ただ、スマホやタブレットは勉強にも使える便利なものなので、子どものタイプによっては、無理やり遠ざけるのではなく、うまく活用する方法を考えるとよいですよ。
なりたい自分を見つける子どもの自律を支える

※写真はイメージ(gettyimages/matimix)
サッカー選手やミュージシャンの夢をどう捉える?
Q:ゲーマーになりたい、ミュージシャンになりたいなど、子どもが実現がむずかしそうな夢を持っているとき、親はどのように反応したらよいでしょうか?
A:どんな夢でも否定することはNGで、まずはその夢を目指す理由=志に注目してみてください。もし理想の職業に就くことがかなわなくても、志をかなえる手段はひとつではないことを伝えるのは、大人の役目です。
たとえばミュージシャンと一言で言っても、今はYouTubeやTikTokなどを通して自分の音楽を配信することができます。会社員として勤務しつつミュージシャンとしても活動する、そのような形でも夢を実現させることができますよね。副業として夢を追うこともできるし、複数の仕事を持ってパラレルに働く生き方もある時代ですから。
社会の変化に合わせてアップデートできるように育てる
Q:安定した仕事に就いて幸せに暮らしてほしいという親の願いを子どもに伝えるのは、よくないでしょうか?
A:子育ての最上位目標は、変化の激しい社会にあって自律して幸せに生きていく力を育むことだと思います。自律して幸せに生きていくために、何を学び、どういう働き方をするかは、ひとりひとりが自由に決めていくものです。安定を求めて、働く環境や生きる道筋をがちがちに固めてしまうと、むしろ変化の大きい社会に対応できなくなってしまうかもしれません。
「子どもをサポートしてあげたい」「守ってあげたい」という親の気持ちが、子どもの自分で考えて決める機会を奪っていたら、自律は遠のきます。親は、子どもをどうサポートするかということよりも、どう手放すかを考えることが必要かもしれません。








































































