こちらの記事も読まれています

生後100日のお祝い「お食い初め」は100日より前や後でもよい?
お食い初めのタイミングとお祝いの手順、料理、日程調整のポイントをまとめて紹介
お食い初めは、赤ちゃんが一生食べ物に困らないようにとの願いを込めて生後100日を迎える頃に行う伝統的なお祝いです。しかし、必ずしも100日に行う必要があるのか、日程を100日より前や後にずらしても良いのか悩んでいる保護者も多いでしょう。今回の記事では、お食い初めは100日より前でもよいのかや実際にいつ行ったか、お食い初めのやり方や料理、日程の調整などについて経験者の声をもとに紹介し、男の子や女の子のお祝いについても触れていきます。100日より前でもよいかなどお食い初めのポイントをおさえて家族の思い出に残るお祝いになるとよいですね。
※この記事の内容は、2025年9月9日に更新されたものです。
【保護者の声】お食い初めは100日より前でも大丈夫?
お食い初めは生後100日目に行わなければならないのか気になる保護者の方もいるでしょう。お食い初めを行う日は地域により異なりますが、周りの保護者たちはどのようなタイミングでお食い初めをしたのでしょう。理由を含め聞きました。
30代ママ
30代ママ
私たち夫婦だけでお祝いする予定だったので、生後100日目の日にお食い初めをしました。日中は赤ちゃんのお世話で手一杯なので食事は事前に用意し、当日は食べ物を食器に移して食べる真似と写真撮影だけになるよう準備しました。
40代ママ
お食い初めは生後100日後の週末にお祝いしました。私の両親も交えてお祝いだったので、100日前後の週末にしようと決め、みんなの都合のよい日程が100日より後だったため先送りした日程で行いました。
お食い初めの日程を100日目の日にするママもいれば、100日より前倒しで行ったり、先送りして100日後に行ったママもいるようです。100日過ぎてもよいのか気になる場合もあるかもしれませんが、一般的には100日前でも問題ないとされています。
お食い初めに親せきを呼ぶかどうか、必要な物はどうやって用意するか、写真撮影をするかどうかなどを考えながら、無理なくお食い初めの準備ができるとよいでしょう。
お食い初めとはどのような行事?
お食い初めの歴史は古く、平安時代から始まったとされる儀式のひとつです。
お食い初めは、赤ちゃんが一生食べ物に困らないようにとの願いを込めて行う大切な儀式で、「お食い初めの儀式」と「歯固めの儀式」の2つを行うことが一般的です。順番としては、「お食い初めの儀式」をして、そのあと「歯固めの儀式」を行うことが多いようです。お食い初めは、生後100日目に行うとされていますが、家族の都合で日程を調整することもよくあります。料理には鯛や赤飯などが含まれ、写真撮影も行われることが多いです。
子どもの誕生を祝うお食い初めについて、いつ行えばよいか迷っているママやパパもいるのではないでしょうか。生後100日の日にぴったりお食い初めをしたいと思っても、家族の都合などで100日より前になったり、100日後になってしまう場合もあるでしょう。今回はお食い初めのタイミングについて周りのママたちに調査を行いました。意味やお祝いのやり方・順番などを含めご紹介します。
お食い初めの意味やお祝いする方法
一般的に生後100日や130日にお祝いすると言われるお食い初めですが、どういった意味が込められた行事なのでしょうか。「お食い初めの儀式」と「歯固めの儀式」のやり方、男の子、女の子それぞれのお祝いの方法とあわせて調査しました。
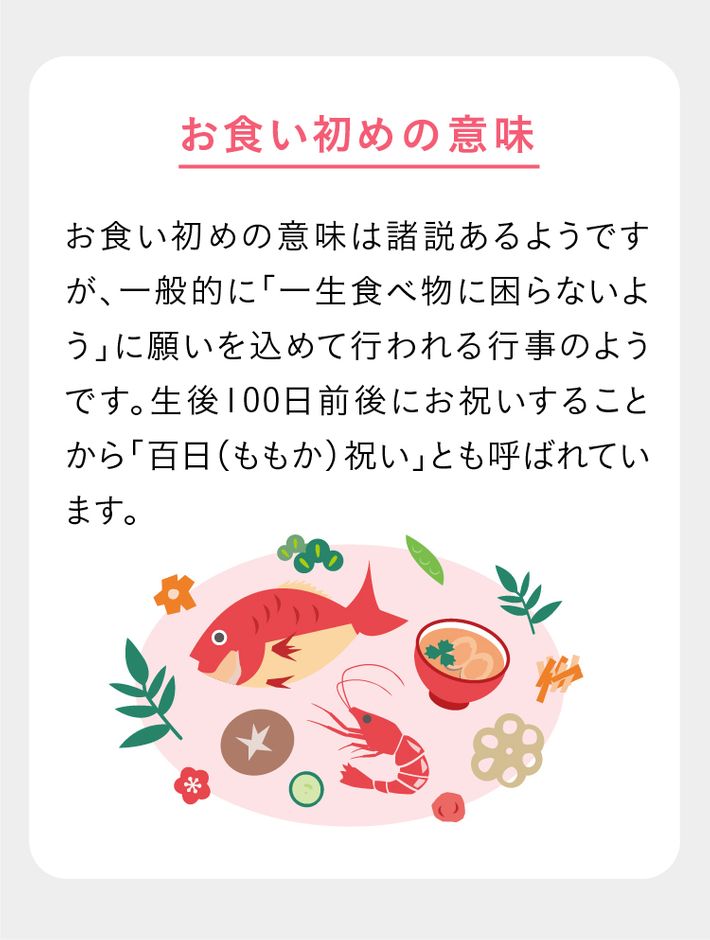
祝い膳を食べる真似をさせる儀式(男の子・女の子別)
お食い初めの儀式は一生食べ物に困らないようにとの願いを込めて、赤ちゃんに祝い膳を食べる真似をさせることでお祝いします。お祝いのやり方などは諸説ありますが、赤ちゃんに食べる真似をさせる人は、長寿にあやかり最年長の方を選ぶとよいようです。
地域の風習により異なる場合もあるようですが、赤ちゃんに食べさせる真似をする人は「養い親」と呼ばれ、最年長の人が食べさせる真似をします。祖父母が参加する場合は、男の子の場合は祖父、女の子の場合は祖母が食べさせます。祖父母がいない場合は、赤ちゃんの性別が男の子なら父親、女の子なら母親が養い親となります。
歯固めの儀式
歯固めの儀式は、石のように丈夫な歯が生えてくるように祈願するものです。氏神様の境内で拾った「歯固めの石」にお箸を軽くあてて、そのお箸を赤ちゃんの歯ぐきに優しくあてます。
お食い初めで準備するもの
お祝い行事であるお食い初めでは、どのようなものを準備したらいいのでしょうか?特に、お祝い膳にどのような料理が必要なのか気になる方もいるでしょう。ここからは、お食い初めで準備するものについて、準備した方法に関する体験談も交えてご紹介します。
祝い膳

karakaru - stock.adobe.com
祝い膳の料理は一汁三菜が必要となります。具体的には、汁物、焼き魚、煮物、香の物、ごはんです。
汁物はハマグリなどを使ったお吸い物、焼き魚は尾頭付きの鯛、ごはんはお赤飯を用意することが多いようです。煮物や香の物には特に決まりはないようです。用意する食材や食べさせる手順は地域によって異なるようなので、祖父母に聞いてみたり地域のやり方を調べてみてもよさそうですね。
生後100日前後でお祝いする場合、離乳食を始めていないご家庭がほとんどかと思います。赤ちゃんが本当に食べてしまわないよう気をつけましょう。
お食い初めの料理の準備方法を聞いてみました。
30代ママ
お食い初めの料理はネット注文しました。慣れない育児で料理を用意する余裕がなく、当日は楽しむことに専念できたのがよかったです。やり方がわからず不安でしたが、注文したセットに丁寧な説明書きがありスムーズに終わりました。
30代ママ
煮物とお吸い物、お赤飯は自分で用意し、鯛の塩焼きはお店で注文しました。酢の物が苦手なので代わりにフルーツを盛りつけるなど、楽しみながら料理の用意ができたと思います。長寿にあやかり、最年長の祖父に食べさせてもらいました。
「赤ちゃんが一生健康で幸せに過ごせるように」という願いが込められている尾頭付き祝い鯛の他、はまぐりのお吸い物や香の物、煮物など用意する品数が多いお食い初め用の料理は、ママやパパにとって負担にならないよう工夫してみてはいかがでしょう。自分たちなりにアレンジを加えて料理を楽しんでいる声もありました。
食器・祝い箸(男の子・女の子別)
祝い膳を盛り付ける食器について、男の子と女の子で違いがあるようです。食器は漆塗りを使うのが正式とされ、男の子なら内側も外側も赤色、女の子なら内側は赤色、外側は黒色の食器を選ぶと言われています。
祝い箸は、柳の木で作られていて両端が細くなっているものが多いといわれています。柳の木は丈夫で生命力があることから、お食い初めの祝い箸に使われるようです。
食器についても、保護者の方に準備方法を聞いてみました。
30代ママ
お食い初めでは出産祝いでいただいたプレートを使いました。お皿が一つなので盛り付けに悩むこともなく、扱いやすかったです。
30代ママ
祖父母からもらった離乳食用の木製のランチプレートをお食い初めで初めて使用しました。お食い初めの写真といっしょに使ったことを伝えると、とても喜んでくれました。
保護者の方からは、赤ちゃん向けの離乳食用の食器をお食い初めで使用したという声が聞かれました。形式にとらわれず準備をしているご家庭が多いのかもしれませんね。
歯固め石

tatsushi - stock.adobe.com
「歯固めの石」はお宮参りのときに神社から授かることもあるようです。お宮参りのときに授からなかった場合、神社で拾ったり、インターネットで購入することもできるようです。地域によっては、タコやアワビ、梅干しなどで代用されることもあるようです。
歯固め石の準備方法も聞いてみました。
20代ママ
お食い初めの祝い膳や歯固め石がセットになっているものをインターネットで購入しました。必要なものがすべてセットになっていたので、当日の準備が簡単に済みました。お祝い膳、歯固めの順番で行いました。
インターネットなどで、お祝い行事であるお食い初めに必要なものがすべてセットになって販売されているようです。当日の準備が簡単になるようなので、保護者の方にとってメリットがたくさんありそうですね。
お食い初めの日程調整のポイント
お食い初めの日程について、100日より前倒しで行う、もしくは先送りして100日より後に行うことも可能です。家族が集まりやすい週末や特別な日程を選ぶことが一般的です。男の子も女の子の性別に関係なく、それぞれの家庭の事情に合わせて行事の日程を調整しましょう。
参加するメンバー
30代ママ
お食い初めは私たち夫婦だけでお祝いしました。双方の両親が遠方に住んでいることもあり、お食い初めは家族だけでお祝いしようとパパと相談し決めました。自宅でお祝いしたので、赤ちゃんも安心して過ごしていました。
30代ママ
私の祖母がお赤飯をたいてくれると言ってくれたので、家族みんなで帰省しお食い初めをしました。実母もいっしょに準備をしてくれたのでありがたかったです。みんなで写真を撮れたのも記念になりました。
両親だけでお食い初めをお祝いする場合もあれば、親戚を交えてお祝いする場合もあるようです。生後100日前後は赤ちゃんのお世話で手いっぱいな場合もあるでしょう。両親、赤ちゃんにとって負担になりにくい方法や人数でお祝いできるとよさそうですね。
料理の準備・お店の予約
お祝いの料理はお店で注文することも、自宅で手作りすることもできます。特に鯛はお食い初めの象徴的な料理として知られています。人気のお店で注文する際は、余裕をもって予約をしておきましょう。赤ちゃんが生まれて間もない頃からお店を探し始める方もいるようです。お食い初めを自宅で行う場合、インターネットで祝い膳を注文したという声も聞かれました。
写真撮影の予約
お祝いの思い出を残すため、写真撮影の計画も重要です。写真館やプロのカメラマンに写真撮影を依頼する場合は、あらかじめ日程を予約しておきましょう。「お食い初め(百日祝い)プラン」の写真撮影を行なっている写真館もあるようです。
当日の衣装もセットになっているプランなども用意されていたという声もありました。衣装などの準備がないのは、保護者の方にとって助かりますね。
家族の予定調整
お食い初めに参加する双方の両親など、家族全員が参加できる日を選ぶことが大切です。遠方からの家族が集まる場合は、早い段階から日程調整が必要です。特に連休などを利用しようと考えている場合は、宿泊先の空きや交通手段も考慮する必要があるでしょう。
100日より後に行う場合
100日を過ぎてからお食い初めを行うことも問題ありません。多くの家庭では都合に合わせて日程を調整しています。行事を楽しむことが目的なので、厳密に100日にこだわらずに日程を決めましょう。
100日よりも後に行う場合のメリットとしては、時間に余裕ができるため、料理や衣装、写真撮影の準備を丁寧に行なうことができる他、お店や写真館の予約も取りやすいかもしれません。
お食い初めで子どもの誕生をお祝いしよう

TMM.com - stock.adobe.com
今回記事では、お食い初めをいつ行ったか、お食い初めのやり方や料理、日程の調整などについて経験者の声をもとに紹介し、男の子や女の子のお祝いについてもご紹介しました。
お食い初めは生後100日目に行わなければならないのか気になる保護者の方もいるでしょうが、生後100日ぴったりにこだわりすぎる必要はないようです。保護者や祖父母、親せきの人などが参加しやすい日程を選んでみてはいかがでしょう。
100日より前でも、100日過ぎても、子どもの幸せを願うことに変わりはありません。それぞれに合った準備の仕方を考え、当日を楽しく過ごせると良いですね。料理や写真撮影を工夫して、素敵な思い出を作りましょう。







































































生後100日目の日は平日でパパのいない日でした。お食い初めの準備を考えるとパパもいる休日の方がやりやすいと思い、日程を前倒しして100日より前にお食い初めをしました。朝から夫婦2人で準備できたので、尾頭付きの鯛の受け取りや食事、写真撮影など気楽に楽しめました。