こちらの記事も読まれています
テープ式とパンツ式のオムツの使い分け。違いや切り替えのタイミング
2018.10.18

テープ式とパンツ式の違いを考えたとき、オムツの価格や大きさの他に、使い分けや切り替えのタイミングが気になるママもいるのではないでしょうか。今回の記事では、それぞれのオムツの特徴やシーン別の使い分けアイデア、切り替えのタイミングなどをママたちの体験談を交えてご紹介します。
テープ式オムツとパンツ式オムツの違い
赤ちゃんにオムツを用意するときに、テープ式オムツとパンツ式オムツには、どのような違いがあるのか気になるママもいるかもしれません。そこで、それぞれのオムツの違いとママたちが感じたメリットについてまとめてみました。
テープ式オムツ
テープ式のオムツは、赤ちゃんにオムツを履かせるときに、テープを貼る位置で赤ちゃんのお腹や太もも周りにあわせてサイズ調整ができるといった特徴があるようです。サイズも新生児用サイズから展開しており、価格が安く経済的なことから、オムツ替えが頻繁な新生児の頃からサイズアップするまで長く使えるかもしれません。
ママたちに聞くと、テープ式のオムツのメリットは、オムツ自体を広げられることから、赤ちゃんを寝かせたままのオムツ替えがしやすいといった声がありました。
パンツ式オムツ

iStock.com/ArveBettum
パンツ式のオムツは、立ったままオムツを替えられるという特徴があるようです。サイズについても、メーカーによっては幅広いことで、赤ちゃんの体にあわせて大きさを選びやすく、オムツが外れる時期まで長く使うことができるかもしれません。
オムツ交換する際、サイドを破るとテープ式のように広げることもできるので、赤ちゃんが寝ていても脱がしやすいといったママの声もありました。また、ウエスト部分がゴムになっていることで、赤ちゃんのお尻にフィットしやすくずれにくいことから、赤ちゃんの成長にあわせて少しずつテープ式オムツから移行していくママもいるようです。
【シーン別】テープ式とパンツ式の使い分けアイデア
それぞれのオムツの両方のサイズが対応している時期は、シーンに応じてオムツを使い分けるといった工夫をすることがあるようです。実際に、ママたちがテープ式とパンツ式それぞれのオムツをどのように使い分けていたのかご紹介します。
夜
「テープ式オムツは、1枚あたりの単価が経済的と考え昼はパンツ式、夜寝るときはテープ式と使い分けていました。1歳くらいまで夜はテープ式を使っていたことで、オムツにかかる費用を抑えることができたと感じています」(1歳2カ月のママ)
夜に1枚当たりの価格の安いテープ式のオムツを使うことで、オムツにかかる費用を抑えるといったアイデアのようです。パンツ式タイプとテープ式タイプを上手に使い分けることができれば、オムツ代の節約につながるかもしれませんね。
うんちのとき
「普段はパンツを使っているのですが、赤ちゃんがうんちをしたときは、替えのオムツはテープ式を使っていました。テープ式オムツは汚れているオムツの下に広げてセットできるので、周りを汚さずにスムーズに交換できたと感じています」(10カ月赤ちゃんのママ)
パンツ式を主に使っていても、うんちをしたときの替えのオムツにテープ式オムツを使うことでオムツ替えがスムーズにいくことがあるようです。場合によっては、お尻をきれいにしている途中でおしっこが出てしまうこともあることから、新しいテープ式オムツをお尻の下に広げておくことで、服や周りが汚れてしまうことを防げるかもしれませんね。
外出時

iStock.com/Jay_Zynism
「外出先のトイレによっては、オムツ交換台がないことがありました。テープ式のオムツは、ズボンを全て脱がさない状態でもオムツがつけられるのでので手早くオムツ交換ができました」(7カ月赤ちゃんのママ)
「赤ちゃんの動きやすさを考えて、外出時は足周りに伸縮性のあるパンツ式のオムツを選んでいました。パンツ式は立ったままオムツを替えられるので、車の中など寝転がるスペースがない場合でも交換しやすく便利でした」(11カ月赤ちゃんのママ)
ママたちは、出かける場所や状況あわせて、外出時にオムツを使い分けることもしていたようです。オムツを替える状況にあった使いやすいオムツを選んで使い分けるのもよいかもしれませんね。
オムツ切り替えのタイミング
テープ式オムツからパンツ式オムツへの切り替えのタイミングが気になるママもいるのではないでしょうか。ママたちが切り替えを考えたきっかけやタイミングについて聞きました。
動き回るようになったら
「寝返りをするようになった頃、テープ式のオムツでは動きに応じて太ももなどに隙間ができることでおしっこやうんちがもれることが気になったので、パンツタイプに切り替えました」(5カ月赤ちゃんのママ)
「オムツ替えのときに、赤ちゃんがはいはいをしようと動き回ることでオムツのテープが留めづらく手間が増えるようになりました。テープタイプでは時間がかかると感じ、足を通すだけでオムツ替えができるパンツタイプに徐々に切り替えていきました」(8カ月赤ちゃんのママ)
赤ちゃんが動くことで、おしっこやうんちがもれてしまうことが気になるときや、テープが留めにくいと感じたタイミングでパンツ式に切り替えることもあるようです。ママのなかには、シーンにあわせて使い分けをしながら少しずつ切り替えたという声もありました。
サイズがあわなくなったら
「テープ式を使っていたのですが、うんちのときに後ろからもれてしまうことが多くなり、パンツ式にした方がよいか迷っていました。サイズアップのタイミングだったので、深履きできるパンツ式に切り替えました」(6カ月赤ちゃんのママ)
赤ちゃんの成長によるサイズアップの他に、赤ちゃんのおしっこやうんちの量がオムツの大きさとあわないと感じたタイミングでパンツ式に切り替えたママもいるようです。メーカーによってオムツのサイズ感やフィット感が違う場合もあるようなので、赤ちゃんにあったタイプを見つけられるとよいかもしれません。
オムツは赤ちゃんにあわせて使い分けよう

iStock.com/kokouu
テープ式オムツとパンツ式オムツは、形状や価格の他に対象としている月齢や大きさなどに違いがあるようです。パンツ式タイプに切り替えるタイミングは、赤ちゃんの成長や状況にあわせるなどさまざまなようで、ママのなかにはどっちを使おうか迷ったという声や、使い分けながら徐々に移行していったという声もありました。
それぞれのオムツの特徴を意識して、赤ちゃんにあったオムツ選びができるとよいですね。



















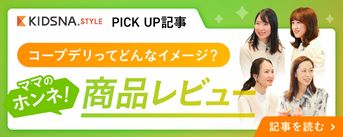


































![【天才の育て方】#19 紀平凱成~聴覚過敏の困難と向き合い感性溢れるピアニストへ[前編]](https://kidsna.com/image/cms/article/thumbnail/2e065453-7729-4ab4-b4be-351c7618be1d.png?dw=344)















