こちらの記事も読まれています

幼児教育に迷う保護者へ。偉人や著名人が送る名言21選
子どもの将来を考え、幼児教育を行う保護者。しかし、思うようにいかなかったり、不安になることも多いでしょう。そんなときに偉人の名言を読むと、心が落ち着いたり、悩みが解消されることもあるかもしれません。偉人の名言とともに、KIDSNA STYLEの取材記事からも幼児教育についての名言を紹介します。
「大切な子どもだからこそ、将来苦労してほしくない」
「高校受験や大学受験で困らないように幼児教育をしっかりとさせてあげたい」
このように子どもを想う気持ちから幼児教育を行う保護者も、ときには「本当にこれでいいのか」「思うようにできない」などと、迷ったり、悩んだりすることもあるでしょう。
本記事では、そんな保護者に読んでほしい、幼児教育に関する名言を紹介します。
幼児教育に効く名言
まずは、偉人が残した幼児教育にまつわる名言を紹介します。
・最も有用な指導は、その課題に対し最小限の言葉をかけること(マリア・モンテッソーリ/1870~1952)
・教育もまた、教育を必要としないだろうか?(カール・マルクス/1818~1883)
・子どもたちを正直でいられるようにすることが、教育の始まりである(ジョン・ラスキン/1819~1900)
・子どもたちに何ができるのか知りたければ、彼らに物を与えるのをやめるべきだ(ノーマン・ダグラス/1868~1952)
・教育は結構なものである。しかしいつも忘れてはならない。知る価値のあるものは、すべて教えられないものだということを(オスカー・ワイルド/1854~1900)

※写真はイメージ(gettyimages/denisik11)
・教育とは炎を燃え上がらせることであって、入れ物を満たすことではない(ソクラテス/紀元前470~399)
・どんな段階でも子どもにはありのままの現実を体験させるようしなければならない。バラの刺を最初から絶対に抜いてはいけない(エレン・ケイ/1849~1926)
・子どもの教育は、過去の価値の伝達にはなく、未来の新しい価値の創造にある(ジョン・デューイ/1859~1952)
・子どもたちに勉強を教えることは、子どもたちに人生の意味を教えることだ(ヴィクトル・ユーゴー/1802~1885)
・子どもたちがやりたいことに、自由になる機会を与えることが、最良の教育だ(ジャン=ジャック・ルソー/1712~1778)
・教育の秘訣は、教えることに情熱を持つことであり、子どもたちに情熱を持って学ばせることである(アナトール・フランス/1844~1924)
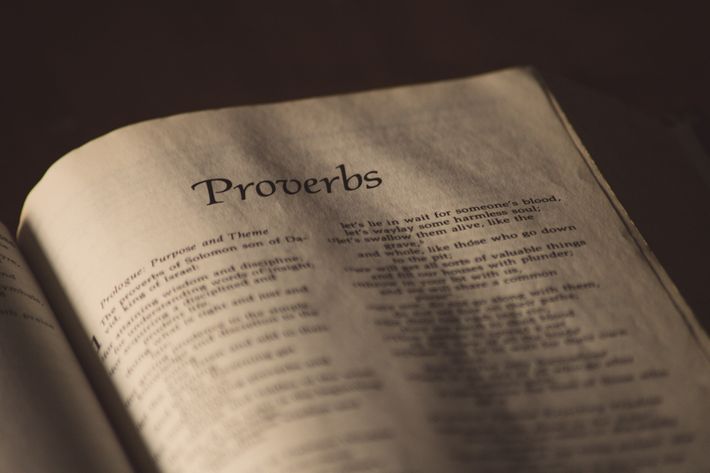
※写真はイメージ(gettyimages/Robby Sheets)
・子どもたちに教える最も重要なことは、子どもたちが自分自身を信じて、自分の夢を追求する勇気を持つことです(ラルフ・ワルド・エマーソン/1803~1882)
・暗いのではなく優しいのだ。のろまではなくていねいなのだ。失敗ばかりではなくたくさんのチャレンジをしているのだ(アルフレッド・アドラー/1870~1937)
・子どもは叱られることよりも、手本を必要としている(ジョセフ・ジュベール/1754~1824)
KIDSNA STYLE過去記事より幼児教育に関する名言を紹介
これまでのKIDSNA STYLEの記事でも、出演いただいた各分野の専門家が、多くの名言を残しています。
“
未就学の時点では、ひらがながひと通り読めて、自分の名前がちゃんと書ければ十分。特別な幼児教育を受けていなくても、その後トップの大学に行っている人はたくさんいます。幼児教育ははっきり言って関係ありません
出典: 花まる学習会代表 高濱正伸
“
小学校受験は、したからといって勉強ができるようになるとか、能力が伸びるとかそういうことではない
出典: 花まる学習会代表 高濱正伸
“
行き過ぎた幼児教育の最大の問題は、愛着形成をやり残してしまうこと
出典: 青山学院大学教授・小児精神科医 古荘純一
“
子ども自身が考えたり感じたり試行錯誤するプロセスが生まれないと、知育にはなりません。よい玩具の条件をあげるとすれば、子どもの知的探求を促すことができるかどうかという点が大事なんです
出典: 玉川大学教授 大豆生田啓友
“
子どもが才能をのびのびと開花させるには、親御さんが子どもの「監督」ではなく「応援団」に徹することが重要です。親御さんが子どもの「監督」ではなく「応援団」に徹することが重要です
出典: 教育評論家 親野智可等
“
最も知能が伸びるとされる幼少期には「好奇心」と「探求心」を育むのが最も重要です。そして、「好奇心」を育むために行うべきことは、早期英才教育ではありません。 教育には順番があり、興味がなければその教育には何の意味もなく、逆に子どものストレスになります。
出典: 脳科学者 澤口俊之
“
他人の子育て論は、あくまで選択肢です。話半分で聞くくらいがちょうどいい。決めるのはパパママ。自信を持って子育てしてください
出典: 現役保育士・育児アドバイザー てぃ先生
そもそも「名言」とは?
そもそも名言というのは、どのような言葉を指しているのでしょうか。辞書をひくと、「事柄の本質をうまくとらえた言葉」と説明があります。また、「名言」の「名」には、「優れている」という意味が含まれています。
つまり、「名言」という言葉には、「事柄の本質をとらえ、人の心に響くほどの優れた言葉」というニュアンスが含まれています。
名言と同じ読みで「明言」という言葉もありますが、意味は全く違います。明言は、「きっぱりと自分の意思を相手に伝える」という意を持ち、「明言する」といったように、動詞として使うことが多い言葉です。
幼児教育の名言を読みたいタイミング
幼児教育において名言が役に立つのはどのようなときでしょうか。

※写真はイメージ(gettyimages/Kaan Sezer)
- 家庭での幼児教育の方針に自信を持てないとき
- 幼児教育に失敗してしまったかもしれないと感じたとき
- 幼児教育のモチベーションが薄れてしまったとき
- 子育てに迷いが生じたとき
このようなときに、偉人や専門家の名言を読むことによって、気持ちが保てたり、また頑張ってみようと思ったりすることにつながるかもしれません。
幼児教育の名言に関する体験談
先輩ママに、幼児教育の名言に関する体験談を聞きました。
6歳児のママ
9歳児のママ
娘は未就学児のころ、絵を描いたり外で遊んだりすることが好きでしたが、周りの子が字を書けたり足し算ができることに少し焦りを感じていました。そんなとき、KIDSNA STYLEの記事で、花まる学習会の高濱先生が、『幼児教育はしてもいいけどしなくてもいい』ということを言っていて、気持ちがラクになったことを覚えています
幼児教育における不安や迷いを緩和する名言

※写真はイメージ(gettyimages/maruco)
子どもの幼児教育のことになると、プレッシャーや不安、迷いを感じる保護者はとても多いでしょう。そんなときに、偉人やKIDSNA STYLEに出演している専門家の名言をぜひ読んでみてください。
気持ちが落ち着いたら、より一層子どもと向き合うことができるようになるかもしれません。お気に入りの名言は手帳などにメモして、いつでも見返すことができるようにするのもよいですよ。











































































小学校受験を考え始めてから、子どものマイペースさに心配になることがありましたが、たまたま目にした 『暗いのではなく優しいのだ。のろまではなくていねいなのだ。失敗ばかりではなくたくさんのチャレンジをしているのだ』というアドラーの名言で、気持ちを切替えることができました