こちらの記事も読まれています
在宅ワークに必要な仕事の書類とは。主婦が家でできる、パソコンで収入を稼ぐ仕事について
2018.05.20

副業などで在宅ワークをしようと考えている主婦の方もいるのではないでしょうか。パソコンを使って家でできる仕事で、収入を稼ぐにはどのようにしたらよいのかと悩むママもいるかもしれません。今回の記事では、仕事の見積もりや契約、請求に関する書類の作成について厚生労働省の資料をもとにご紹介します。
在宅の仕事に関する書類
副業などで在宅ワークをする上で、どのような書類が必要になるか知っておきたい主婦の方もいるのではないでしょうか。主婦がパソコンを使って家でできる副業をする際には、見積書や契約書、請求書の発行が必要になる場合もあるようです。在宅での仕事をする上で知っておくとよい書類についてご紹介します。
仕事の見積について
厚生労働省の資料によると、仕事が見つかったら契約を結ぶ前に見積書を作成する場合があるようです。
見積書発行までの流れ
仕事の依頼を受けたら、依頼内容と自分の能力やスケジュールなどが合うかどうか考えてから、請け負うか決めるとよいようです。仕事を請け負うことはクライアントとの契約となるので、スケジュールに合わない納期などで仕事が間に合わないといったことがないように、無理をしないことも大切になってくるかもしれません。
主婦の方は、家族の体調不良などで予定が変わることも考え、余裕を持ってスケジュールを組めるとよさそうですね。クライアントによっては、請け負うか決める前におおむねの見積もりを求められる場合もあ見積書発行までの流れるようです。
見積書に記載すること
仕事を請け負うと決めたら、クライアントから仕事内容について詳しく聞き、作業のイメージがつかめたら依頼内容やスケジュールなどをよく検討した上で、見積書を発行するとよいようです。厚生労働省の資料によると、見積書に含める項目について以下のような内容が紹介されています。
・見積もりの日付
・見積者の住所や連絡先、担当者
・見積もりの件名(行う作業のこと)
・見積もり項目、数量、単位、
単価、金額など
見積書に必要な項目については、クライアントや状況によってもさまざまなので契約前に確認しておくとよいかもしれません。
在宅ワーカーが確認すること

iStock.com/Yagi-Studio
見積もりの金額について決める際には、いくら稼ぐことができるかについて考える場面も出てくるかもしれません。副業などで家でできる仕事を行う場合も、利益をきちんと確保できるように考えることが大切になってくるようです。
利益を考える際には、自分が稼ぐと決めた収入の目標金額のほかにも、相場やクライアントとの付き合いの程度、他に競争相手がいるかといったことも目安になるようです。
仕事の契約について
見積書を発行し発注者と内容などを確認したあと、契約書が交わされたら実際の契約となるようです。
契約書を発行する目的
契約内容などを書面にすることは、仕事に関する権利について確認することにつながるようです。主婦を含む在宅ワーカーが遭遇するトラブルは少額の案件も多く、弁護士などの専門家に相談する費用をかけることが難しい場合もあるようです。書面があることによってトラブルが起きたときの交渉も進めやすくなるかもしれません。
主婦が安心して副業を行うためにも、契約書の確認は大切になってくるようです。パソコンを使って契約書のやり取りを行う主婦の方は、必要な書類をプリントアウトして保管しておくとよさそうですね。
契約書に記載すること
契約書には2種類あり、基本契約と個別契約があるといわれています。同じ相手と繰り返し受注や発注が行われることを想定して、毎回の仕事に共通する内容が書かれたものを基本契約というようです。
基本契約と比べて、仕事の納期など契約する際の個別の内容に関することが書かれたものを個別契約と呼び、注文された仕事の内容や収入となる報酬額、さまざまな経費の取扱いなど、個別の内容がより詳しく記載されている場合があるようです。
契約書に記載される項目については、仕事やクライアントよっても異なるようです。主婦の方は、実際に在宅での作業に取り掛かる前には、契約書に目を通しておくとよいかもしれませんね。
在宅ワーカーが確認すること
報酬や納期などの条件についてお互い納得できたら契約書を交わすことになるので、内容についてしっかりと確認しておくことも大切になってくるようです。仕事を完了しても、発注者が指定している条件を満たしていない場合は追加で修正作業を行う場合もあるようです。
仕事に関するトラブルを避けるためにも、追加の作業をするときにどのような対応が必要になるか事前に話し合っておくとよいかもしれません。
代金の請求について
契約をして仕事が始まり、代金の請求を行うまでの流れについて見ていきましょう。
請求書発行までの流れ
発注された在宅ワークの作業が完了したら、指定された期日までに納品を行う必要があり、納品が完了した時点で発注者に連絡するなどして受け取りの確認をするとよいようです。
納品した仕事が仕様を満たしているかなどの検査があり、満たしていなければ追加で修正作業が求められる場合もあるようです。検査に合格したら納品完了となり、納品書をもとに請求書を発行する流れになるようです。
請求書に記載すること
請求書に記載する請求金額は、納品の期日までに完了した仕事の合計報酬額を発注者と確認し金額を決めるようです。決まった請求金額や支払い日をもとに、請求書を発行するとよいようです。
厚生労働省の資料によると、請求書には請求する合計金額のほかにも給与の振込先に関する情報なども必要になってくるようです。発行日や単価などクライアントによって書き方は異なる場合もあるようなので、取引の際に把握しておくとよさそうです。
在宅ワーカーが確認すること
請求書を作成したら、それぞれの項目について記入漏れがないか確認してから発行するようにしましょう。
請求書を発行し支払い日を迎えたら、きちんと入金がされているか確認することも忘れないようにしたいですね。また、明細書と入金の金額、請求書と違いがないかなども確認し、違いがある場合は発注者に確認して説明してもらうことも大切になってくるかもしれません。
書類の作り方について知っておこう

iStock.com/kohei_hara
パソコンを使った在宅ワークなどにかかわる書類についてご紹介しました。主婦が家でできる副業を始める際にも、それぞれの書類について知っておくことで仕事に役立てられるかもしれません。
きちんと収入を得るためにも、実際に稼ぐ目標金額などを目安に見積書を作成することや、請求書に記載した支払日に振り込まれているかの確認も大切になりそうです。契約書の内容についても記載されていることはさまざまなようなので、発注者と十分に確認し合えるとよいですね。
※記事内で使用している参照内容は、2018年5月20日時点で作成した記事になります。






















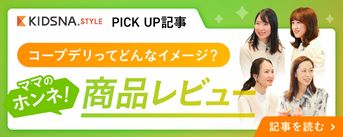
































![【天才の育て方】#19 紀平凱成~聴覚過敏の困難と向き合い感性溢れるピアニストへ[前編]](https://kidsna.com/image/cms/article/thumbnail/2e065453-7729-4ab4-b4be-351c7618be1d.png?dw=344)















