こちらの記事も読まれています
赤ちゃんのオムツの替え時は?サイズアップやパンツタイプのオムツに替えた時期
2018.10.13

赤ちゃんにオムツを使っていると、サイズやオムツのタイプの替え時が気になるママもいるのではないでしょうか。今回は、オムツのサイズの替え時とパンツタイプへの替え時、オムツのサイズやタイプを替えるときに気をつけたことを体験談を交えてご紹介します。
オムツのの替え時はいつ?
赤ちゃんのオムツは、どのようなタイミングで替えたらよいのか気になるママもいるのではないでしょうか。初めて育児を経験する場合、オムツをサイズアップするタイミングに迷うママもいるかもしれません。ママたちは、どのような場面でオムツの替え時を考えたのでしょう。
オムツのサイズの替え時
赤ちゃんのオムツには、新生児用やS、M、L、ビッグなどさまざまなサイズがあるようです。実際に、ママたちがオムツのサイズアップを考えた、替え時の目安をご紹介します。
対象の体重や月齢を超えた頃
「オムツのパッケージに対象とされている目安の体重が書いてありました。赤ちゃんの体重が対象体重に近くなった時期にサイズアップを検討しました」(20代ママ)
「オムツの対象体重や月齢を参考にしてサイズアップしました。同じサイズでも通常用とハイハイ用があるときは、子どもの動きや成長にあわせて選びました」(30代ママ)
オムツのパッケージには、対象となる目安の体重や月齢が記載されているようです。体重を目安にしながら、実際の使い心地を見てオムツをサイズアップしたというママの声もありました。
テープを留めにくくなったとき

iStock.com/arsenik
「テープタイプのオムツを使っているとき、テープを留める位置が外側に近づくと留めにくいと感じました。テープが留めにくくなってきたことをきっかけにサイズアップを検討しました」(30代ママ)
子どもが大きくなると、テープを留めにくいと感じるママもいるようです。テープを留める位置が外側になると外れやすかったので、大きいサイズへの替え時だと感じたというママの声もありました。
オムツ漏れをするようになった頃
「おしっこが漏れてしまうことが多くなった頃にサイズアップしました。オムツは大きいサイズの方が吸収する面積も多いようで、オムツ漏れがしにくくなりました」(40代ママ)
赤ちゃんが大きくなると、1度にするおしっこの量も増えたと感じるママもいるようです。オムツをサイズアップすることで、オムツ漏れを防げる場合もあるかもしれませんね。
パンツタイプのオムツへの替え時
テープタイプのオムツを使っている場合、パンツタイプへはいつ替えればよいのか、替え時が気になるママもいるかもしれません。ママたちに、テープからパンツタイプのオムツへ替えた時期を聞いてみました。
ねんね期
「生後3カ月の頃、足をバタバタさせるようになり、テープタイプのオムツでは替えにくいと感じることがありました。オムツをパンツタイプにすると、赤ちゃんが動いていても替えやすかったです」(30代ママ)
「うちの子は、生後6カ月の頃に寝返りをするようになりました。オムツ交換中も寝返りすることが多かったので、寝返り中にも履かせやすいパンツタイプが使いやすかったです」(20代ママ)
ねんね期の赤ちゃんでもオムツ交換中に体を動かす場合、パンツタイプに替えるとオムツを履かせやすかったというママの声もありました。赤ちゃんの動きが少ない夜はテープタイプを使うなど、状況にあわせて使いわけるのもよいかもしれませんね。
ハイハイ期
「生後8カ月の頃にハイハイをするようになったことで、パンツタイプのオムツへの替え時を検討しました。オムツ交換中にハイハイで動き出してしまうときも、追いかけて履かせられるパンツタイプは使いやすかったです」(40代ママ)
赤ちゃんがハイハイをするようになると、寝かせたままではオムツ交換がしにくいと感じるママもいるようです。パンツタイプなら、赤ちゃんがハイハイをしていても片足ずつ通して履かせやすかったというママの声もありました。
たっち期

© mannpuku - Fotolia
「生後9カ月の頃、つかまり立ちをするようになったのでパンツタイプに移行しました。机につかまっている間にサッとオムツ替えができるので便利だと思いました」(30代ママ)
「生後11カ月頃、つたい歩きをするようになったら横になってオムツを交換することを嫌がるようになりました。立った状態で交換できるパンツタイプにすると機嫌よくオムツ交換をすることができました」(20代ママ)
つかまり立ちやつたい歩きをするようになったことを、パンツタイプへの替え時と考えたママもいるようです。たっち期はパンツタイプの方がスムーズに履かせやすかったというママの声もありました。
オムツを替えるときに気をつけたこと
オムツのサイズやテープやパンツなどのオムツのタイプを替えるとき、どのようなことに気をつけたらよいのでしょうか。
フィット感のあるものを選ぶ
「テープからパンツタイプに替えるとき、お腹や太もも周りがゆるすぎず、きつすぎないものを選びました。体にフィットするオムツは履き心地もよさそうに見えました」(30代ママ)
「うちの子はウエストが細めなので、体重を目安にオムツをサイズアップすると、お腹周りに隙間ができてしまうことがありました。テープタイプだとウエスト幅が調整しやすいので、体にフィットさせやすかったです」(40代ママ)
赤ちゃんの体型にフィットするサイズやタイプを選ぶように気をつけたママもいるようです。ギャザーの伸びがよく、体にフィットしやすいタイプのオムツは、赤ちゃんが活発に動いても隙間ができにくくオムツ漏れもしにくいかもしれませんね。
少量ずつ買い足す
「普段はオムツを3パックずつまとめ買いしています。サイズアップの時期が近づいてきたときは、オムツが余らないように1パックずつ買い足しました」(40代ママ)
「初めてパンツタイプに替えるとき、子どもの体型にあうか試したいと思いました。小さめのパックを1つ買い、履き心地を確認してから買い足すようにしました」(30代ママ)
オムツをサイズアップしたり、テープからパンツタイプに移行したりするとき、まとめ買いをしないように気をつけたママもいるようです。オムツの替え時のタイミングを見ながら少量ずつ買い足すと、無駄になってしまうオムツが少なくなったというママの声もありました。
赤ちゃんにあわせてオムツの替え時を考えよう

iStock.com/iryouchin
テープタイプのオムツを使っている場合、パンツタイプへの替え時やサイズアップの目安が気になるママもいるのではないでしょうか。
赤ちゃんが立てるようになった頃にパンツタイプのオムツにしたり、対象の体重や月齢を目安にサイズアップしたりと、さまざまなタイミングで替え時を考えたママもいるようです。赤ちゃんの体型や動きにあわせて、使いやすいオムツを選んでみてはいかがでしょうか。



















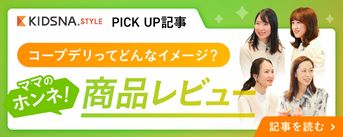


































![【天才の育て方】#19 紀平凱成~聴覚過敏の困難と向き合い感性溢れるピアニストへ[前編]](https://kidsna.com/image/cms/article/thumbnail/2e065453-7729-4ab4-b4be-351c7618be1d.png?dw=344)















