こちらの記事も読まれています
赤ちゃんの靴下はいつから?手作りなど用意の仕方やサイズや種類の選び方
2018.10.05

赤ちゃんの靴下はいつから履かせるのとよいのか気になるママもいるのではないでしょうか。今回は、靴下をいつから履かせたのかや手作りなどの用意の仕方、かわいいデザインや靴下みたいなデザインなど靴下の選び方と、赤ちゃんに靴下を履かせるときに気をつけたことをママたちの体験談を交えてご紹介します。
赤ちゃんの靴下はいつから?
赤ちゃんの足が冷たいと感じるときなど、靴下を履かせたほうがよいのか、いつから使おうか気になるママもいるかもしれません。ママたちは赤ちゃんにいつから靴下を用意したのでしょうか。
「靴下をいつから用意しようか悩みましたが、冬生まれだったので産前に何足か購入しました。生後1カ月をすぎて外気浴をするときなど、外が寒いときは履かせていました」(10カ月のママ)
「お座りができるようになった頃から、芝生や砂場など外で遊ぶときに靴下を使おうと考えました。足底部分がゴムでできている、靴や靴下みたいに使えるタイプを用意すると、いつから靴を買おうか悩んでいたときも便利でした」(7カ月のママ)
「鼻水が出ていたり、朝起きたばかりで室内が寒かったりするときに靴下を使っています。生後2カ月の頃から使い始めました」(11カ月のママ)
いつから赤ちゃんに靴下を用意したのかは、ママたちによってもさまざまなようです。冬の防寒や外遊びをするときなど、場面によって臨機応変に使うことを考えるとよいかもしれませんね。室内ではあまり使わず、まだ歩けない時期の外出時に履かせることがあったというママの声もありました。
赤ちゃん用の靴下の用意の仕方
赤ちゃんの靴下を用意しようと思ったとき、購入する以外にも手作りができるのかなど気になるママもいるかもしれません。赤ちゃんの靴下をどのように用意したのか、ママたちに聞いてみました。
購入する

iStock.com/AndreyPopov
「デパートで購入しました。赤ちゃんの靴下は小さくてデザインのかわいいものがたくさんあるので、赤ちゃんが靴下を履く場面を想像しながら選ぶ時間も楽しめました」(5カ月のママ)
「夏生まれの赤ちゃんに綿素材の薄めの靴下を用意したかったので、ベビーグッズ売り場で購入しました。店員さんに選ぶポイントなども教えてもらえました」(5カ月のママ)
赤ちゃんの靴下を用意するとき、購入して用意したママもいるようです。カラフルなかわいいデザインや素材の違いなど、種類豊富なもののなかから選びたいときは、実際にお店に行ってみると選びやすいかもしれませんね。
手作りする
「妊娠中に毛糸編みの手作りの靴下を用意しました。自分で作ると好みにあわせて作ることができ、サイズアウトした後も思い出としてとっておく楽しみができました」(10カ月のママ)
「手芸が好きなので、手作りで帽子とお揃いの靴下を用意しました。手作りするとサイズ調整ができ、赤ちゃんの足のサイズにあったものが作れるのがよいところです。ママ友の子どもにも手作りすることがあります」(9カ月のママ)
赤ちゃん用のかわいい靴下を手作りしたママもいるようです。妊娠中に手作りをすると、赤ちゃんに会える日を楽しみに思えたというママの声もありました。
赤ちゃんの靴下の選び方
赤ちゃんの靴下を選ぶとき、種類や選び方を知りたいママもいるかもしれません。ママたちにどのように靴下を選んだのか聞いてみました。
サイズ

iStock.com/KulikovaN
「赤ちゃんの足のサイズはどのように測ればよいのかと思い、お店で店員さんに相談しました。紙に十字を書き、縦と横の線が交わるところに赤ちゃんのかかとの中心をあわせ、つま先のいちばん長いところに印をつけて長さを測るとよいと教えてもらいました」(4カ月のママ)
「お店に赤ちゃんの月齢や身長にあわせたサイズの目安表があったので、それを参考に靴下を選びました。赤ちゃんの足は大きくなるのも早いので時期毎にサイズを見直しています」(10カ月のママ)
サイズ表を使って、赤ちゃんの月齢を目安に靴下のサイズを選んだり、紙を使った測定方法を試したママもいるようです。お店に行き、実際に赤ちゃんの足に靴下をあわせながらサイズを選んだというママの声もありました。
素材やつくり
「赤ちゃんの足はたくさん汗をかくと聞きました。汗をかいても快適にすごせるように、吸湿性の高い綿素材を選びました」(6カ月のママ)
「縫い目が少ないものは赤ちゃんにとっても履き心地がよいと思いました。肌に優しい素材やつくりを重視して選んでいました」(3カ月のママ)
素材やつくりを確認して赤ちゃんの靴下を選んだママもいるようです。靴下は直接肌に触れるものなので、なるべく肌ざわりのよいものを選んだというママの声もありました。
使いたいシーンにあわせる
「よちよち歩くようになり、家のなかで歩く練習をするときは、底がゴムでできている靴下みたいに見えて、靴としても使えるタイプを選びました。足の底がゴム素材なので、普通の靴下より滑りにくく使いやすかったです」(11カ月のママ)
「外遊びをするときは、汚れが目立たなそうな濃い色の靴下を使ったり、お出かけのときは履くだけで靴を履いたように見えるかわいいデザインの靴下を使ったりしています」(9カ月のママ)
お出かけや歩く練習など、使うシーンや目的によって靴下を選ぶのもよいかもしれません。靴下みたいなデザインのもの以外にも、伝い歩きができる時期の赤ちゃんには、滑り止めがついた靴下を選んだというママの声もありました。
靴下を履かせるとき気をつけたこと
靴下を履かせるときに気をつけるポイントを知りたいママもいるかもしれません。靴下を履かせるときに気をつけていたことについて、ママたちに聞いてみました。
脱げにくい工夫をする
「赤ちゃんがバタバタと足を動かすうちに、靴下が脱げてしまうことがありました。靴下の上からレッグウォーマーを重ねて使うようにしたら脱げにくくなりました」(10カ月のママ)
靴下を履かせるとき、脱げにくい工夫をしているママもいるようです。短い靴下は脱げやすかったので、ハイソックスを使ったというママの声もありました。
場面に応じて使う
「冬は寒いだろうと思い、靴下を履かせる機会も多かったです。暖房のきいた室内ですごすときは、暑そうにしていたら脱がせるようにしていました」(11カ月のママ)
赤ちゃんに靴下を履かせるときは、気温差などを考えながら場面にあわせて使っているママもいるようです。夏でも冷房が気になるときは、薄手素材のハイソックスを履かせていたというママの声もありました。
赤ちゃんの靴下は場面にあわせて選ぼう

© tatsushi - Fotolia
赤ちゃんの靴下はいつから用意すればよいのか気になるママもいるかもしれません。購入するだけでなく、手作りで靴下を用意すると赤ちゃんの足のサイズにあった靴下が用意しやすかったというママもいるようです。
かわいいデザインや靴としても使える靴下みたいなタイプなど、さまざまな種類のなかから、季節や必要に応じて使いやすい靴下を選べるとよいですね。




















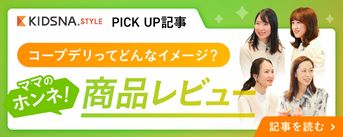
































![【天才の育て方】#19 紀平凱成~聴覚過敏の困難と向き合い感性溢れるピアニストへ[前編]](https://kidsna.com/image/cms/article/thumbnail/2e065453-7729-4ab4-b4be-351c7618be1d.png?dw=344)














