こちらの記事も読まれています
1歳半の子どもが歯磨きを嫌がるときはどうする?ママたちの対策と工夫
2018.10.24

1歳半くらいの子どもが歯磨きを嫌がるとき、スムーズに歯磨きをする方法を知りたいと思うママもいるかもしれません。今回の記事では、1歳半の子どもの歯磨きをするときの悩みや子どもの好きな歯ブラシを使うなどの歯磨きを嫌がるときの対策、歯磨きが嫌いにならないための工夫を体験談を交えてご紹介します。
1歳半の子どもの歯磨き事情
子どもが1歳半頃になると、乳歯の数が増えたり、健診などで歯磨き教室が開かれたりすることで、子どもの歯磨きについて考える機会が増えるママもいるのではないでしょうか。
その反面、子どもが歯磨きを嫌がったりすると、どうしたらスムーズに歯磨きができるのかと考えることもあるかもしれません。子どもが嫌がらずに歯磨きをするためにはどうしたらよいでしょうか。
1歳半の子どもの歯磨きをするときの悩み
1歳半くらいになると、自分の気持ちを主張するようになる子どももいるようで、気に入らないことがあると嫌がることもあるかもしれません。1歳半くらいの子どもの歯磨きをするときの悩みを、ママたちに聞いてみました。
自分で歯磨きをしない

iStock.com/solidcolours
「歯ブラシを渡しても、遊んでいるだけで歯磨きをしようとしません。歯磨きに興味をもってもらえるとよいなと思っています」(30代ママ)
「歯ブラシを渡そうとすると、嫌がって逃げることがあります。私が仕上げ磨きだけしていますが、自分でも歯磨きをするように習慣づけたいと考えています」(20代ママ)
子どもが自分で歯磨きをしないことや、歯磨きを嫌がることで悩んでいるママもいるようです。歯ブラシを見るだけで泣くこともあり、毎日の歯磨きがスムーズにできずに困っているというママの声もありました。
仕上げ磨きを嫌がる
「仕上げ磨きをしようとして仰向けに寝かせると嫌がって暴れるので、仕方なく両手を私の脚でおさえながら歯磨きをしています」(30代ママ)
「仕上げ磨きのときに、嫌がって口をなかなか開けてくれません。無理やり口を開けると泣いてしまうので、奥の方まで歯ブラシが届かず、磨き残しがあるのではと悩んでいます」(30代ママ)
子どもが仕上げ磨きを嫌がって泣くことや、仕上げ磨きが十分にできていないのではと悩むママもいるようです。嫌がることを無理にすると、ますます歯磨き嫌いになるのではと心配しているというママの声もありました。
1歳半の子どもが歯磨きを嫌がるときの対策
1歳半の子どもが歯磨きを嫌がるとき、歯磨きがスムーズにできる方法や工夫を知りたいママもいるかもしれません。実際に、子どもが歯磨きを嫌がるときにママたちがしていた工夫を聞いてみました。
お気に入りのパペットを使う

© TK6 - Fotolia
「お気に入りのパペットを私の手にはめて、パペットが歯ブラシを持っているように見せて歯磨きをしました。子どもがパペットに注目している間に歯磨きをしています」(30代ママ)
「子どもの歯磨きをする前に、パペットの歯を磨く真似をしています。『次は〇〇くんの番だよ』と言って子どもの歯を磨くと、自分から口を開けてくれることがありました」(20代ママ)
お気に入りのパペットを使って歯磨きをしているママがいるようです。動物のぬいぐるみや人形など、子どものお気に入りのおもちゃを使って歯磨きをすると、自分もやってみようと思うこともあるかもしれませんね。
曲にあわせて磨く
「歌を歌いながら歯磨きをしています。歌が終わると歯磨きも終わりだとわかると、歌っている間はがんばって口を開けてくれるようになりました」(40代ママ)
「動画サイトで幼児番組の歯磨きの映像を見せながらいっしょに歯磨きをしています。『お友だち上手だね。〇〇ちゃんもがんばろう』と言うと泣かずに歯磨きができました」(30代ママ)
音楽にのせて歯磨きをすると、子どもも楽しい雰囲気で歯磨きができるかもしれません。歯磨きする絵本を見たり歌をいっしょに歌ったりすると、スムーズに口を開けてくれたというママの声もありましした。
お気に入りの歯磨きグッズを使う
「フルーツ味のする歯磨きジェルを歯ブラシにつけると、スムーズに歯磨きができました。すすぎがいらないものだったので、1歳半の子でも使うことができました」(30代ママ)
「子どものお気に入りのキャラクターがついた歯ブラシを購入しました。それを使うといつもより乗り気で歯磨きをしてくれました」(30代ママ)
歯ブラシなど、お気に入りの歯磨きグッズを用意すると子どもが歯磨きに関心を持ってくれたと感じるママもいるようです。歯ブラシの種類を何種類か試して、子どもが嫌がらない歯ブラシを探したというママの声もありました。
子どもを歯磨き嫌いにさせない工夫
歯磨きを嫌がる子どもに無理に歯磨きをすると、ますます嫌がるようになるのではないかと悩むママもいるかもしれません。子どもが歯磨き嫌いにならないための工夫には、どのような方法があるでしょうか。
短時間で済ませる
「日によって歯磨きを嫌がるときがあります。なるべく短時間で終わらせるようにして、嫌がらないときによく磨くようにしています」(30代ママ)
子どもが嫌がるときは、短時間で歯磨きを済ませるようにしているママもいるようです。仕上げ磨きを嫌がるときは、朝と昼は自分で磨くだけにして、夜だけ仕上げ磨きをするようにしたというママの声もありました。
力加減に気をつける
「強く磨きすぎると、子どもも痛みで歯磨きを嫌がるようになるかもしれないと思いました。仕上げ磨きをするときは、力を入れずに優しく磨いています」(30代ママ)
仕上げ磨きをするときは、力加減に気をつけるのもよいかもしれません。自分もリラックスした気分で歯磨きをすると、力を入れすぎずに磨けるというママの声もありました。
がんばったことを褒める
「嫌がってしまうこともありますが、いつも歯磨きが終わったら必ず抱っこをして『がんばったね』と笑顔でたくさん褒めるようにしています。毎回の積み重ねが自信に繋がるとよいなと思っています」(30代ママ)
歯磨きの後は、スキンシップをとったり言葉に出して子どものがんばりを褒めているママもいるようです。ママが嬉しそうにしていると、子どもの自信に繋がる場合もあるのかもしれませんね。
1歳半の子どもが楽しめる歯磨きの仕方を考えよう

iStock.com/bee32
1歳半頃の子どもが歯磨きをするとき、嫌がらずに歯磨きをする方法を知りたいと思うママもいるかもしれません。子どもが歯磨きを嫌がるときは、曲にあわせて磨いたり、お気に入りの歯ブラシなどを使ったりして、子どもが楽しめる時間になるよう意識しているママもいるようです。
短時間で磨いたりたくさん褒めたりと、1歳半頃の子どもにあわせて歯磨きの仕方を工夫できるとよいですね。




















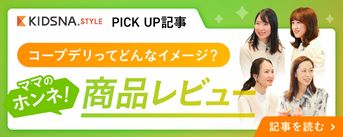
































![【天才の育て方】#19 紀平凱成~聴覚過敏の困難と向き合い感性溢れるピアニストへ[前編]](https://kidsna.com/image/cms/article/thumbnail/2e065453-7729-4ab4-b4be-351c7618be1d.png?dw=344)















