こちらの記事も読まれています
新生児が喜ぶ音楽は?ママたちにきく、英語教育用の音楽やクラシックなどの聴かせ方
2018.05.06

新生児にクラシックなどの音楽を聴かせたいと考えているママもいるのではないでしょうか。新生児は英語教育用の音楽やロックを喜ぶのか、音量はどのくらいがよいのか気になるママもいるかもしれません。新生児に聴かせていた音楽、音楽を流す場面、新生児と音楽を楽しむポイントについてママたちの体験談をご紹介します。
新生児に音楽を聴かせている?
ママたちは新生児に音楽を聴かせているのでしょうか。赤ちゃんがお腹にいる頃から音楽を聴かせていたママたちは、赤ちゃんが産まれてからも続けて聴かせているかもしれません。音楽にはさまざまなジャンルがあるので、赤ちゃんが喜びそうな音楽を選んで聴かせているママもいるようです。
新生児に聴かせていた音楽
ママたちはどのような音楽を新生児に聴かせていたのでしょうか。どのようなジャンルの音楽を新生児が喜ぶと感じているのか聞いてみました。
クラシック
「新生児の頃はクラシックをよく聴かせていました。お腹の中にいる頃から私が聴いていた音楽を、赤ちゃんにも聴かせるようにしていました」(30代ママ)
「クラシックのオーケストラの曲などを聴かせていました。音がはっきりしている音楽が赤ちゃんにも聴きやすいかもしれないと思い、メリハリのある曲を選んでいました」(30代ママ)
妊娠中にクラシックを聴くとリラックスできたので、赤ちゃんが産まれてからもいっしょに聴くようにしていたというママがいました。ママが心地よく感じるクラシックを聴けば、赤ちゃんも気分がよくなり喜ぶかもしれません。
童謡

iStock.com/fatesun
「新生児の頃から私が知っている童謡をよく歌ってあげていました。私が気持ちよく歌うと、赤ちゃんが喜ぶような感じがしました」(40代ママ)
「赤ちゃんは子どもの声を喜ぶのではないかと思い、児童合唱団の歌う童謡をよく聴かせていました」(40代ママ)
童謡は昔からママたちに親しまれている音楽なので、新生児に聴かせようと考えるママもいるようです。ママ自身が歌ってあげると、赤ちゃんもママも心地よい時間を過ごせるかもしれません。
英語の歌
「新生児の頃から英語に親しめたらと思い、子ども用の英語の歌を聴かせていました」(40代ママ)
「新生児にロックを聴かせてもよいか迷いましたが、英語の教育になるかもしれないと思い、イギリスの穏やかな曲調のロックを選んで聴かせていました」(40代ママ)
新生児の頃から英語の音楽を聴かせることで、英語教育に役立つかもしれないと考えるママもいるようです。言葉が分からない時期から英語に触れる環境をつくるのもよいのかもしれません。
音楽を聴かせるタイミング
ママたちはどのようなタイミングで新生児に音楽を聴かせているのでしょうか。
赤ちゃんが泣いたとき

iStock.com/Mitsuo Tamaki
「新生児の頃は頻繁に泣き、理由もよく分からないことが多かったので、泣いたときには音楽を聴かせていました。音楽を聴かせると泣き止むこともありました」(30代ママ)
「赤ちゃんが泣いたときには、リズムのはっきりした音楽を聴かせるようにしていました。新生児の頃はクラシックや童謡など、さまざまなジャンルのものを聴かせていました」(40代ママ)
新生児の頃は、泣く理由が分からずに悩むママもいるかもしれません。赤ちゃんがお腹の中にいる頃ママが聴いていた音楽やリズミカルな音楽を流すと、赤ちゃんがしばらく泣き止んだというママの声もありました。
赤ちゃんを寝かしつけるとき

iStock.com/Yagi-Studio
「新生児の頃は、赤ちゃんのためのクラシックを寝かしつけるときに聴かせていました。オルゴール調の優しい音楽にしていました」(30代ママ)
「私が童謡や子守唄を歌って寝かしつけていました。私の歌声を聴いて気持ちよく寝てくれることもありました」(40代ママ)
新生児の頃から、赤ちゃんを寝かしつけるときに音楽を聴かせていたというママもいるようです。静かなクラシックやママが歌う子守歌など、赤ちゃんを寝かしつけるためにママたちはさまざまな音楽を選んでいるようです。
ママがリラックスしたいとき
「赤ちゃんが新生児の頃は、ときどき私の好きな音楽も流していました。赤ちゃんのお世話で疲れたときに、お気に入りの穏やかなロックなどを聴くとリラックスできてよかったです」(30代ママ)
「赤ちゃんの機嫌がよいときに、私の好きな英語の音楽を流すことがありました。私のリフレッシュにも赤ちゃんの教育にもなるのではないかと思いました」(40代ママ)
赤ちゃんのためだけでなく、ママ自身のリフレッシュのためにいっしょに好きな音楽を聴くこともよいかもしれませんね。
新生児と音楽を楽しむポイント
新生児と音楽を楽しむために、ママたちはどのような工夫をしているのでしょう。また、どのようなことに気をつけているのでしょう。
抱っこをして揺れながら
「赤ちゃんといっしょに音楽を聴くときには、赤ちゃんを抱っこして音楽に合わせてゆらゆら揺れるようにしていました。体を揺らしていると、赤ちゃんが気持ちよさそうにしていました」(30代ママ)
「英語の歌を聴くときもクラシックを聴くときも、音楽に合わせて少しゆらゆらするようにしました。音楽に合わせて動くと私のリフレッシュにもなるように感じて、赤ちゃんといっしょにときどき楽しんでいました」(40代ママ)
新生児の頃から音楽を聴きながら体を揺らすようにしていたというママがいるようです。音楽に合わせてママが動くと、いっしょに揺れる赤ちゃんも心地よいかもしれませんね。
音量の調節
「新生児の頃、赤ちゃんが起きているときは音がよく聞こえるように大きめの音量で音楽を聴かせていました」(40代ママ)
「新生児の頃は、起きているときと寝かしつけるときの音楽の音量を調節するように気をつけていました。寝かしつけるときは、少しずつ音量を下げ、眠ったら音楽を止めるようにしました」(30代ママ)
赤ちゃんの機嫌がよいときや泣いているとき、寝るときなど、赤ちゃんの様子に合わせて音楽の音量を調節するとよさそうです。新生児の頃は、起きているときや泣いているときは音量を上げて、寝るときには音量を下げるようにしていたというママの声もありました。
新生児といっしょに音楽を楽しもう

iStock.com/Yagi-Studio
ママたちが新生児に聴かせている音楽のジャンルはさまざまのようです。新生児にどのような音楽を聴かせようかと考えたときには、英語教育のための歌や赤ちゃんが喜ぶクラシック、ママがリフレッシュするためのロックなど目的やシーンに合わせて選ぶのもよさそうです。音量を調節しながら新生児といっしょに音楽を楽しめるとよいですね。




















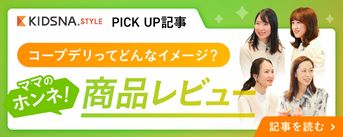
































![【天才の育て方】#19 紀平凱成~聴覚過敏の困難と向き合い感性溢れるピアニストへ[前編]](https://kidsna.com/image/cms/article/thumbnail/2e065453-7729-4ab4-b4be-351c7618be1d.png?dw=344)















