こちらの記事も読まれています
【体験談】新生児のお風呂はいつから?お風呂の入れ方やコツ、お風呂グッズなど
2018.05.04

新生児の沐浴の方法は習うけれど、新生児期を過ぎた赤ちゃんのお風呂の入れ方はわからない、というママもいるのではないでしょうか。首がすわっていない赤ちゃんとの毎日のお風呂で、ママたちが活用したお風呂グッズや、泣くときの入れ方のコツ、お風呂上がりの白湯などの水分補給について体験談を交えてご紹介します。
新生児のお風呂はいつから
新生児はいつからお風呂に入れるのでしょうか。一般的には、新生児期(生後28日未満)は沐浴で済ませ、1カ月健診で許可がおりてから大人と同じお風呂に入れるようです。ママたちはどのようなタイミングで赤ちゃんをお風呂デビューさせているのでしょうか。
「健診が終わったその日の夜からいっしょのお風呂に入りました」(30代ママ)
「1人で入れるのは不安だったので、パパがいる休日に手伝ってもらいながらお風呂に入れました」(20代ママ)
「首がすわっていない赤ちゃんをお風呂に入れるのが難しかったので、首がすわってベビーバスが手狭に感じた3カ月くらいでお風呂デビューしました」(30代ママ)
他にも赤ちゃんの体調に合わせたり、周りに手伝ってくれる人がいるといった環境が整ったりしたタイミングで、新生児期を過ぎた赤ちゃんをお風呂に入れ始めたというママがいました。
【体験談】新生児期を過ぎてからのお風呂の入れ方

Pecherskiy_kz/Shutterstock.com
新生児期を過ぎた赤ちゃんを毎日お風呂に入れるのは、大変に感じるかもしれませんがママたちはどのように入れていたのでしょう。ママたちの体験談をご紹介します。
使うものを準備する
「バスタオルを敷いた座布団、着させやすいようにセットした着替え、保湿クリーム、オムツ、おしりふき、ガーゼを脱衣所に準備していました」(30代ママ)
保湿クリームやオムツ、おしりふきは脱衣所に常備しておくと、毎日準備する手間が省けそうです。脱衣所に座布団やマットを敷いて赤ちゃんを寝かせるスペースを作るママもいました。
お風呂上がりの赤ちゃんの身支度がスムーズにできるよう、着替えをセットしておくなど細かいところまで準備しておくと、ママも慌てずにすみそうです。
ママが先にお風呂に入る
「脱衣所に座布団を敷いて赤ちゃんを寝かせておき、ママが先にお風呂に入り体や髪を素早く洗います。その間は赤ちゃんから目を離さないようお風呂のドアは開けっぱなしにしていました」(30代ママ)
赤ちゃんを洗う前に、自分の体や頭を洗うようにしていたママがいました。ママが体を洗っている間は、脱衣所に座布団やバウンサーなどを置いて赤ちゃんを待たせておくとよいかもしれません。ママが先にお風呂に入れば浴室内も温まりそうです。
新生児を膝の上で優しく洗う
「利き手と逆の手で、赤ちゃんの頭や首を支え、自分の膝の上で赤ちゃんの体を優しく洗います。濡らしたガーゼで先に顔をふき、その次に石鹸をつけて体を洗っていました」(30代ママ)
ママと赤ちゃんの体が濡れていると、すべってしまうこともあるかもしれません。赤ちゃんが動いても滑らないように、赤ちゃんの体とママのひざの間にガーゼを1枚広げておくなど、工夫をしていたママもいました。
ママといっしょに湯船につかる
「沐浴のときのように、頭や首を支えながら、ママといっしょに湯船につかりました。赤ちゃんの体が湯船に浮かぶので、沐浴のときよりもあまり手に重さを感じずに過ごせました」(20代ママ)
ママたちは、あまり長湯をさせずに赤ちゃんの体が温まる頃に湯船から上がり、体を冷やさないようにしっかり水気をふき取るよう意識していたそうです。
ママたちが使っていたお風呂グッズ
新生児期を過ぎた赤ちゃんとのお風呂で、ママたちはどのようなお風呂グッズを使っていたのでしょうか。ママたちに活用していたお風呂グッズについて聞いてみました。
スポンジマット
「赤ちゃんを寝かせられる、お風呂用のスポンジマットを使っていました。お座りができる月齢まで役立ちました」(30代ママ)
スポンジマットはお風呂の床に置いて使うお風呂グッズで、クッション性があるので、赤ちゃんを寝かせることができるようです。手がふさがっているときや、赤ちゃんを支えている腕がつらくなったときなど、短い時間だけ赤ちゃんを寝かせていたというママがいました。
赤ちゃんといっしょに浴室に入り、ママの体を洗っている間は赤ちゃんをスポンジマットに寝かせておくママの声もありました。
バスローブ

iStock.com/Yuji_Karaki
「お風呂上がりにすぐ赤ちゃんの身支度に取りかかれるよう、自分はバスローブを羽織っていました」(20代ママ)
「夏場などの気温が高い時期、ママが先にお風呂に入っている間やお風呂上がりに、赤ちゃんには着脱が素早くできるバスローブを着せていました」(30代ママ)
バスローブは着脱も早くでき、バスタオル代わりにもなるので、ママも赤ちゃんも使えそうなお風呂グッズです。
手ぬぐい
「沐浴のときから使っていた手ぬぐいが便利です。頭を洗っているときには体にかぶせたり、湯船ではお湯から出ている赤ちゃんのお腹や肩にかけたりして使いました」(50代ママ)
赤ちゃんのお湯から出ている部分や、待たせている間の体を冷やさないために、ガーゼより大きめの手ぬぐいを使っているママもいました。手ぬぐいの素材や大きさもさまざまあるようなので、ママの使いやすいものを試してみるとよさそうです。
赤ちゃんをお風呂に入れるときのコツ
毎日入れるお風呂で、ママたちはどのような工夫をしていたのでしょうか。赤ちゃんをお風呂に入れるときのコツを聞いてみました。
機嫌のよい時間帯をねらう
「夕方の授乳後、機嫌のよいタイミングでお風呂に入りました」(30代ママ)
「毎日の生活リズムをみていると、18時から19時頃はだいたい起きていることが多かったので、その時間帯に入れていました」(30代ママ)
お風呂の時間はしっかり決めず、子どもの様子や毎日の生活リズムを観察しながら、機嫌のよい時間帯に合わせることを意識していたママもいるようです。
お風呂上がりの水分補給をしっかり
「新生児から離乳食を始めた5カ月くらいまでは、水分補給は母乳でした。お風呂上がりに授乳時間をしっかりとるように意識していました」(30代ママ)
「お風呂上がりは少しの白湯を飲ませていました。白湯はお風呂に入る前に忘れず準備して、冷ましておきました」(50代ママ)
新生児期を過ぎた赤ちゃんのお風呂上がりには、母乳やミルクで水分補給するようにしていたというママがいました。お風呂に入る前に授乳させたときは、白湯を飲ませることもあったというママの声もありました。
お風呂上がりの赤ちゃんの様子をみながら、授乳や白湯の量を調整するとよさそうです。
泣くときは無理をしない
「赤ちゃんが泣くときは、赤ちゃんだけ先に洗ってお風呂時間を素早く済ませ、自分は後で入り直しました」(30代ママ)
「沐浴のときから使っていたガーゼを赤ちゃんのおなかにかけると、安心するのかあまり泣かずにすみました。それでも泣き始めたときは無理して入れず、お風呂を切り上げました」(30代ママ)
赤ちゃんは毎日機嫌よく入ってくれるとは限らないようです。泣いているときは時間を短くしたり、赤ちゃんを待たせる時間を省いたりしながら、無理せず入れるとよさそうです。
赤ちゃんとのお風呂を楽しもう

polkadot_photo/Shutterstock.com
新生児期を過ぎた赤ちゃんとのお風呂は、慣れるまではコツが必要となるかもしれません。お風呂上がりに慌てないように着替えや白湯など必要なものをしっかり準備し、首がすわっていない時期から使える便利なお風呂グッズを活用するとよさそうです。
赤ちゃんが泣くときは無理をしないで、毎日の赤ちゃんとのお風呂を楽しめるとよいですね。




















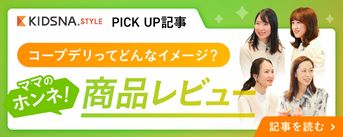
































![【天才の育て方】#19 紀平凱成~聴覚過敏の困難と向き合い感性溢れるピアニストへ[前編]](https://kidsna.com/image/cms/article/thumbnail/2e065453-7729-4ab4-b4be-351c7618be1d.png?dw=344)














