こちらの記事も読まれています
早生まれの七五三はいつ?「満年齢」と「数え年」についても
前撮り、後撮りのタイミングもご紹介
2019.08.23

子どもが無事に成長したことをお祝いする七五三。「七五三については知っているけど、早生まれの七五三についてはどうすればいい?」と思っているママとパパもいるのではないでしょうか。まずは満年齢と数え年の年齢の数え方をおさらいし、早生まれの七五三はいつおこなったらよいのか、記念撮影のタイミングについてもご紹介します。
七五三をおこなう年齢の数え方をおさらい
年齢の数え方には「満年齢」と「数え年」がありますが、そもそも七五三は何歳でおこなうものなのか確認してみましょう。
満年齢
生まれた日を0歳として、以降1年ごとに歳を加えてゆく数え方
現在、日本で一般的に使われている数え方です。
数え年

iStock.com/MicroStockHub
生まれた年を1歳として、以降毎年、元旦ごとに歳を加えてゆく数え方
数え年は、何月生まれであっても元旦でいっせいに歳をとります。昔は兄妹児が多かったため、公的制度・地域行事での年齢の数え方のタイミングが異なるのは煩雑だとして、この数え方がとられていたようです。
正式には、数え年で子どもが3歳・5歳・7歳になる歳に七五三をおこなうとされているようです。しかし、現在は満年齢で実施するご家族も多いようですね。また、兄妹がいる場合、七五三をまとめておこなうために数え年でも4歳や6歳のときにおこなうこともあるようです。
子どもが早生まれの場合は、同じ学年の子どもたちと同じ年に七五三のお祝いをしたほうがよいのか、翌年まで待ってからお祝いをしたほうがよいのか迷ってしまいますよね。
早生まれの七五三のお祝いはいつおこなえばよいのでしょう。
早生まれの七五三はいつおこなう?
七五三は一般的に11月15日におこなうとされていますが、早生まれの子どもが数え年で七五三をおこなうとすると、数え年が3歳のとき満年齢は2歳。数え年が5歳のとき満年齢は4歳。数え年が7歳のとき満年齢は6歳となります。
早生まれの場合、生まれ月が遅い分、遅生まれ(4月2日~12月31日生まれ)の子どもより身体が小さい子どももいるかもしれません。写真に残る姿がほかの子どもよりも小さいのではないか、と心配になるママもいるかもしれません。
特に最初の七五三である3歳のお祝いは、早生まれであれば満年齢で2歳8~10カ月のときにおこなうことになります。普段着ない衣装を着て、長時間過ごすことが難しい子どもや、ご祈祷中に座っていられない子どももいるかもしれませんよね。
満年齢でおこなうとすると、3歳8~10カ月になっているので、一年前より落ち着いて七五三のお祝いができるようになっているでしょう。
現在は、満年齢おこなう家族も増えているようなので、子どもの成長に合わせて七五三をする年を決めてもよいかもしれません。心配であれば、親戚に聞いてみたり、地域の風習を確認してみてもよいでしょう。
早生まれの男の子・女の子の七五三

iStock.com/yasuhiroamano
一般的には七五三のお祝いは以下の年齢でおこなうようです。

それぞれの年齢には以下のような由来があります。
3歳・・・髪を伸ばし始める「髪置き」(かみおき)
5歳・・・男の子が初めて袴を着る「袴着」(はかまぎ)
7歳・・・女の子が初めて着物に帯を装い始める「帯解き」(おびとき)
ただし、3歳の男の子は地域によっておこなわない場合もあるようです。
特に早生まれだと満2歳でおこなうことになるため、親戚に確認したり、同じ地域に住むママ友はいつ七五三をおこなうのか聞いてみてから実施するか決めてもよいかもしれませんね。
記念撮影のタイミング
子どもの成長を祝う一大イベントである七五三の写真は、写真館で収めたいというママやパパも多いでしょう。
当日以前に撮影する前撮り、七五三当日に撮影する同日撮影、後日撮影する後撮り。早生まれの子どもにとって、いつ撮影するのがよいのでしょう。
前撮り
前撮りのよいところは、時間に余裕があるところでしょう。事前に衣装を着ることができるため、着慣れすることができるのもよいですね。早い写真館だと春頃から撮影することができるようです。
ただし、早生まれの子どもでイヤイヤ期と重なる場合など、成長に合わせて撮影を待ったほうがよい場合もありそうです。
同日撮影
同日撮影は、七五三当日に記念撮影とお参りをまとめて済ませられるところがよいでしょう。遠方からおじいちゃん、おばあちゃんがお祝いに来てくれる場合などは、みんなで記念撮影することができますね。
ただし、衣装を着る時間が長くなったり、写真館から神社への移動で忙しくなるため、子どもが機嫌よく過ごせるか注意が必要です。
後撮り
後日撮影する後撮りも、前撮りと同じように時間に余裕ができるため、子どもが疲れる前に撮影できるところがよいでしょう。前撮りと比べると写真館の日程も押さえやすいようで、ゆったりと撮影できるのもよいですね。
後撮りは一般的に12月~1月頃までに済ませる場合が多いようです。1,2カ月の差とはいえ、七五三当日よりも成長した姿を撮影できるため、早生まれの子どもにとっては特によいかもしれません。
年賀状に七五三の記念写真を使用したい場合は、写真館に年賀状で使用したいことを伝え、12月中に撮影を終えるとよいでしょう。
早生まれの七五三は子どもに合わせておこなおう

七五三
毎日、子どものことを見ていると、些細な成長を見逃してしまうかもしれません。七五三というイベントで、子どもの成長を実感できるのは幸せなことですよね。
七五三で大切なことは、子どもの成長をお祝いすることでしょう。お祝いする時期は、早生まれの子どもが、機嫌よく過ごせるタイミングで成長に合わせておこなうのがよいかもしれません。
子どもが無事に成長したことに感謝し、家族で楽しい七五三を迎えられるとよいですね。




















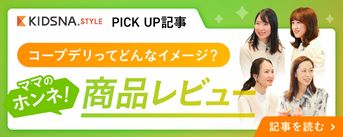

































![【天才の育て方】#19 紀平凱成~聴覚過敏の困難と向き合い感性溢れるピアニストへ[前編]](https://kidsna.com/image/cms/article/thumbnail/2e065453-7729-4ab4-b4be-351c7618be1d.png?dw=344)















